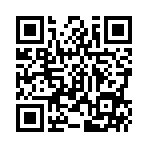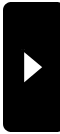2011年11月23日
東京都が首都圏大規模災害時の帰宅困難者対策を条例化
国と東京都、経済団体の三者が「大規模災害時の帰宅困難者」の対策協議会を開催し、企業は3日分の食料や水の備蓄を行うことを基本方針として申し合わせたとのことです。これの伴い、東京都は企業に備蓄を求める条例案を都議会に提案する予定で、首都圏周辺の県や市にも条例の制定を呼びかけたいとしています。

(NHKニュースより)
続きを読む

(NHKニュースより)
続きを読む
2011年11月21日
東京都が電力供給事業
東京都が2014年度を目途に臨海副都心に送電網を整備し、電力供給事業に参入すると発表しました。東京電力の送電網を使用せず、民間事業者の発電施設から周辺のオフィスビルに直接電力を送れる様にし、大災害で東京電力の電力が停止しても安定供給が出来る体制を築くとのこと。
従来電力会社以外の発電事業者が電力供給する場合は、下図の様に電力会社の送電網を借りて、使用料(託送料)を払う必要があり、その負担が重いために電力自由化の妨げの一つと言われていました。

(出所:㈱エネットHPより)
しかし、東京都がその送電網を独自に設置し、託送料を無料とするとのことで、電力料金の値下げも可能とのことです。
続きを読む
従来電力会社以外の発電事業者が電力供給する場合は、下図の様に電力会社の送電網を借りて、使用料(託送料)を払う必要があり、その負担が重いために電力自由化の妨げの一つと言われていました。

(出所:㈱エネットHPより)
しかし、東京都がその送電網を独自に設置し、託送料を無料とするとのことで、電力料金の値下げも可能とのことです。
続きを読む
2011年11月21日
ふじのくに「総合特区指定申請中」
内閣府の「総合特区指定」第一次募集において、応募申請中であった全国合計88件(静岡県関係は6件)について専門家等による第一次,第二次評価結果が出て、次のステップの「ヒアリング」に進めた静岡県関係案件は2件だった様です。ヒアリング日程は11月21日(月)に静岡県浜松市の「未来創造『新・ものづくり』特区」、11月22日(火)に静岡県の「ふじのくに先端医療総合特区」です。
総合特区制度は「国際戦略総合特区」と「地域活性化総合特区」に分類されており、国により指定特区に認定されれば、規制緩和、税制優遇措置、補助金等様々な特典が得られことになるようです。(2011年6月成立の「総合特区法」による)
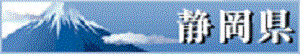 続きを読む
続きを読む
総合特区制度は「国際戦略総合特区」と「地域活性化総合特区」に分類されており、国により指定特区に認定されれば、規制緩和、税制優遇措置、補助金等様々な特典が得られことになるようです。(2011年6月成立の「総合特区法」による)
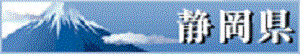 続きを読む
続きを読む2011年11月19日
エネルギーハーベスティング技術(環境発電技術)
11月19日(土)SBSテレビ「報道特集」で「エネルギーハーベスティング技術」と言う聞きなれない言葉の内容について報道されていました。「エネルギーハーベスティング技術」とは「環境発電技術」で、私達の身の周りに存在する熱、振動、光、等の微弱エネルギーを、センサー技術等を駆使して電気信号に変換し、活用しようとするものとのことです。例えば下図の様なイメージです。

(出所:NTTデータ経営研究所「エネルギーハーベスティングコンソーシアム」HPより)
番組では、京都大学の「電波発電」、㈱村田製作所の「振動発電、温度差発電、光発電」、ブリジストンの「路面状態感知装置付タイヤ」、ローム㈱の「屋内測位インフラ(屋内GPS)」、企業不明(?)「蛍光灯光発電」、等が紹介されました。その他、ヘルメットやランニングシューズに埋め込まれた「振動発光体」等もその一例で、バッテリーの要らない世界を展開していました。
続きを読む

(出所:NTTデータ経営研究所「エネルギーハーベスティングコンソーシアム」HPより)
番組では、京都大学の「電波発電」、㈱村田製作所の「振動発電、温度差発電、光発電」、ブリジストンの「路面状態感知装置付タイヤ」、ローム㈱の「屋内測位インフラ(屋内GPS)」、企業不明(?)「蛍光灯光発電」、等が紹介されました。その他、ヘルメットやランニングシューズに埋め込まれた「振動発光体」等もその一例で、バッテリーの要らない世界を展開していました。
続きを読む
2011年11月18日
「京都議定書」と「ポスト京都議定書」
この11月下旬に南アフリカ共和国・ダーバンで第17回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP17)が開催されますが、2012年で期限が切れる「京都議定書」に代わる「ポスト京都議定書(将来の国際的な温暖化対策の枠組み)」は決まりそうもなく、2013年以降も京都議定書をそのまま延長しようと考える国と、日本を筆頭に、そのままの延長に反対する国とに分かれています。
そもそも、京都議定書(2008~2012年)は当初話し合いに加わっていた米国が国内の反対勢力のために、ブッシュ元大統領時代に離脱しており、世界の2大CO2排出国である米国と中国(発展途上国と言うことで削減枠組み対象外)が加わらない「京都議定書」をそのまま延長しても、甚だ不公平と言うのが日本を筆頭に反対している国の主張です。
それに対して延長賛成国は、中国の様に、未だ経済発展優先でCO2削減枠組みに入りたくない思惑の国と、折角努力して来た「京都議定書」が期限切れとなった後、削減枠組みが何もなくなり、空白期間が出来てCO2排出が野放しになるよりは、未だましと考える国(欧州連合:EU)とがあります。

(出所:日刊温暖化新聞HPより「2008年国別CO2排出量」)
続きを読む
そもそも、京都議定書(2008~2012年)は当初話し合いに加わっていた米国が国内の反対勢力のために、ブッシュ元大統領時代に離脱しており、世界の2大CO2排出国である米国と中国(発展途上国と言うことで削減枠組み対象外)が加わらない「京都議定書」をそのまま延長しても、甚だ不公平と言うのが日本を筆頭に反対している国の主張です。
それに対して延長賛成国は、中国の様に、未だ経済発展優先でCO2削減枠組みに入りたくない思惑の国と、折角努力して来た「京都議定書」が期限切れとなった後、削減枠組みが何もなくなり、空白期間が出来てCO2排出が野放しになるよりは、未だましと考える国(欧州連合:EU)とがあります。

(出所:日刊温暖化新聞HPより「2008年国別CO2排出量」)
続きを読む