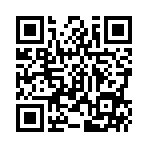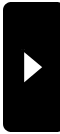2012年05月29日
「国連気候変動会合」実質進展なし
ドイツ・ボンで開催されていた京都議定書の次の枠組みを話し合う「国連気候変動枠組み条約」の事務レベル会合が約2週間の日程を終了し、5月25日閉幕した。昨年末の第17回締約国会議(COP17)以降、初の公式会議だったが、先進国と新興国の意見の隔たりばかりが目立った会合であったとのこと。
今年12月で期限切れとなる京都議定書第1約束期間の後の第2約束期間をどうするかも議題の一つであったが、本来の作業計画の策定の議論には入れず先送りされた模様。
日本は第2約束期間には参加しない意向を表明済みで、2013年以降の二酸化炭素排出削減目標は提出していない。又、オーストラリアやニュージーランドは第2約束期間への態度すら明らかにしていない。
厳しい状況下で、各国・地域は年末にカタール・ドーハで開かれるCOP18に向け議論を続けることになるとのことです。

(出所:WWFホームページ) 続きを読む
今年12月で期限切れとなる京都議定書第1約束期間の後の第2約束期間をどうするかも議題の一つであったが、本来の作業計画の策定の議論には入れず先送りされた模様。
日本は第2約束期間には参加しない意向を表明済みで、2013年以降の二酸化炭素排出削減目標は提出していない。又、オーストラリアやニュージーランドは第2約束期間への態度すら明らかにしていない。
厳しい状況下で、各国・地域は年末にカタール・ドーハで開かれるCOP18に向け議論を続けることになるとのことです。

(出所:WWFホームページ) 続きを読む
2012年05月27日
世界のCO2排出量過去最高を記録!
国際エネルギー機関(IEA)は5月24日2011年に世界で排出された二酸化炭素(CO2)が、前年比3.2%増の316億トンに増え、過去最高を記録したと発表しました。
世界の2006~2010年の平均増加量は6億トン/年で、2011年は約10億トン/年となり、大きく上回ったとのこと。燃料別では石炭が45%、石油が35%、天然ガスが20%となっています。
世界最大の排出国である中国は前年比9.3%増(7億トン以上)、インドの排出はロシアを抜き、中国、米国、欧州連合(EU)に次ぐ世界第4位になった模様。中印などの新興国は高成長を維持しており、企業の生産活動の拡大や、自動車購入などの消費の伸びが排出増に繋がっています。
先進国では米国は1.7%減、EUは1.9%減であったが、日本は前年比2.4%増で11億8000万トンとなり、2年連続の増加となった様です。これは原発の停止に伴う火力発電の増加によるものです。

(出所:IEAホームページ)
続きを読む
世界の2006~2010年の平均増加量は6億トン/年で、2011年は約10億トン/年となり、大きく上回ったとのこと。燃料別では石炭が45%、石油が35%、天然ガスが20%となっています。
世界最大の排出国である中国は前年比9.3%増(7億トン以上)、インドの排出はロシアを抜き、中国、米国、欧州連合(EU)に次ぐ世界第4位になった模様。中印などの新興国は高成長を維持しており、企業の生産活動の拡大や、自動車購入などの消費の伸びが排出増に繋がっています。
先進国では米国は1.7%減、EUは1.9%減であったが、日本は前年比2.4%増で11億8000万トンとなり、2年連続の増加となった様です。これは原発の停止に伴う火力発電の増加によるものです。

(出所:IEAホームページ)
続きを読む
2012年05月18日
大気中のCO2濃度400ppm超の意味
気象庁が観測する大気中のCO2濃度月平均が観測史上初めて400ppmを超えたとの発表がありました。気象庁の定点観測点として、岩手県大船渡市、沖縄県与那国島、東京都小笠原村南鳥島の3ヶ所があり、岩手県大船渡市の観測点では3月:401.2ppm、4月:402.2ppmとなったとのこと。3ヶ所の年平均では2010年:392.8ppm、2011年:394.4ppmで、やはり濃度が上昇しています。

(出所:NHKニュース)
世界では各国の測定機関が「世界気象機関(WMO)」の運営する「温室効果ガス世界資料センター(WDCGG)」にデータを提供し、ここで取りまとめてwebサイトで公表しています。(日本では気象庁がこのwebサイトを運営している)

(出所:WDCGGホームページ 世界のCO2観測点)
では、大気中のCO2濃度年平均400ppm超にはどんな意味があるのでしょうか。
「国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」が「地球温暖化による気温上昇を2℃程度に抑える目安」と位置付けた値が400ppmとなります。これを超えれば、気温上昇を制御できなくなる可能性があると言うものです。 続きを読む

(出所:NHKニュース)
世界では各国の測定機関が「世界気象機関(WMO)」の運営する「温室効果ガス世界資料センター(WDCGG)」にデータを提供し、ここで取りまとめてwebサイトで公表しています。(日本では気象庁がこのwebサイトを運営している)

(出所:WDCGGホームページ 世界のCO2観測点)
では、大気中のCO2濃度年平均400ppm超にはどんな意味があるのでしょうか。
「国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」が「地球温暖化による気温上昇を2℃程度に抑える目安」と位置付けた値が400ppmとなります。これを超えれば、気温上昇を制御できなくなる可能性があると言うものです。 続きを読む
2012年05月12日
BSフジのプライムニュース「太陽の異変」を見て
昨夜(5月11日)20:00~21:55、BSフジのプライムニュースで「太陽に異変、地球寒冷化の可能性」を見ました、これは、本ブログで5/6付で紹介した立花隆さんの文藝春秋5月号の記事「太陽の謎」に関連する内容のもので、ゲストは国立天文台常田佐久教授と広島大学大学院長沼毅准教授でした。
常田教授のお話は今年4月19日国立天文台で発表した、「 『ひので』 による今回の観測の意義と最近の太陽活動について」の内容によるものです。「ひので」はわが国が世界に誇る国産人工衛星で、太陽(特に黒点)観測を目的とし、2006年9月に打ち上げられ現在も稼働中で、時々刻々と観測データを地球に送り続けています。
番組の前編はこの太陽活動の観測結果による異変についての解説で、その異変とは、5/6の本ブログで紹介した内容と同様です。(黒点増減周期と太陽南極、北極の磁極反転の異変)
太陽黒点の増減を観測し始めた400年前のガリレオ・ガリレイの時代から、周期に異変のあった時期は過去2回あり、1810年頃と1680年頃で、この時は小氷期でロンドンのテムズ川が氷結したり、日本でも冷害による大飢饉があったとの記録が残っているようです。

(出所:英ウィキペディア テムズ川凍結画1814年)

(出所:英ウィキペディア テムズ川凍結画1683~1684年)
そこで、ここからは科学的推論になりますが、現在の黒点の増減の様子が過去2回の小氷期に似ており、従って近未来に小氷期が来るであろうと言うものです。又、寒冷化の原因は、太陽から来る熱・光エネルギーそのものが弱まるのではなく、磁力線が弱まることによって磁力線のバリヤーが弱まり、宇宙から地球に降り注ぐ宇宙線が強くなって、雲の核になる物質が増え、それによって雲が増え、そのために太陽エネルギー(熱・光)が遮られて寒冷化するという訳です。
続きを読む
常田教授のお話は今年4月19日国立天文台で発表した、「 『ひので』 による今回の観測の意義と最近の太陽活動について」の内容によるものです。「ひので」はわが国が世界に誇る国産人工衛星で、太陽(特に黒点)観測を目的とし、2006年9月に打ち上げられ現在も稼働中で、時々刻々と観測データを地球に送り続けています。
番組の前編はこの太陽活動の観測結果による異変についての解説で、その異変とは、5/6の本ブログで紹介した内容と同様です。(黒点増減周期と太陽南極、北極の磁極反転の異変)
太陽黒点の増減を観測し始めた400年前のガリレオ・ガリレイの時代から、周期に異変のあった時期は過去2回あり、1810年頃と1680年頃で、この時は小氷期でロンドンのテムズ川が氷結したり、日本でも冷害による大飢饉があったとの記録が残っているようです。

(出所:英ウィキペディア テムズ川凍結画1814年)

(出所:英ウィキペディア テムズ川凍結画1683~1684年)
そこで、ここからは科学的推論になりますが、現在の黒点の増減の様子が過去2回の小氷期に似ており、従って近未来に小氷期が来るであろうと言うものです。又、寒冷化の原因は、太陽から来る熱・光エネルギーそのものが弱まるのではなく、磁力線が弱まることによって磁力線のバリヤーが弱まり、宇宙から地球に降り注ぐ宇宙線が強くなって、雲の核になる物質が増え、それによって雲が増え、そのために太陽エネルギー(熱・光)が遮られて寒冷化するという訳です。
続きを読む
2012年05月09日
広報ふじの「富士市温暖化対策補助制度」について
今日、各戸に配布された「広報ふじ」に「富士市温暖化対策補助制度」の内容が詳しく掲載されています。これはさる3月23日にロゼシアターにて国・県・市の「平成24年度地球温暖化対策事業説明会」で説明された内容の内、富士市の事業に関するものです。

(広報ふじ5/5号 No.1031)
この中で若干判りにくい表現がありますが、市の広報なので、具体的な商品名やメーカー名を出しにくいためと思われます。
詳しくは市の環境総務課に問い合わせるのが適当ですが、筆者の理解するところで簡単な解説を加えて見たいと思います。
構成は
(1)事業者向け「中小企業者温暖化対策事業費補助金(新設)
・新エネルギー設備や省エネルギー設備の導入に対して補助金が交付されます。
①新エネルギー設備とは・・政令により指定された、太陽熱利用、地熱発電、風力発電、太陽光発電などを行うための設備で、外部へのエネルギー供給を行うもの→(筆者注)政令ではこの他に「雪氷熱利用」、「バイオマス発電」、「バイオマス熱利用」、「バイオマス燃料製造(アルコール燃料、バイオディーゼル、バイオガスなど)」、「塩分濃度差発電」、「温度差エネルギー」、「未利用水力を利用する水力発電(出力1000kw以下のものに限る)」などがあります。
②省エネルギー設備とは・・富士市環境アドバイザーによる(無料)診断、又は国・県が実施する無料省エネルギー診断に基づく設備
→(筆者注)無料診断を受けて省エネルギー設備と認定されたものが対象となるので、省エネ診断を受けることが必須要件。
・補助金の対象となる事業は次の通り
①温室効果ガス総排出量を10%以上削減する事業→(筆者注)上記いずれかの無料省エネ診断を受けると明らかになる。
②温室効果ガス排出削減量が年5トン以上の事業→(筆者注)上記と同じ
③売電を目的とする事業→(筆者注)自家消費目的のものは対象外
④富士市環境エネルギー推進協議会が推奨する機器を導入する事業→(筆者注)推奨されるには富士市に審査を申請し、審査の結果、「推奨機器」に認定される必要があります。
(補助金額についてはここでは省略)
(2)市民向け「市民温暖化対策事業費補助金(新設)
・補助金対象事業になるには次の「A」と「B,C,Dのいずれか」と組み合わせて実施する事業
(A)太陽光発電システム・・最大出力3kw以上で、発生した電気を電力会社へ供給できる状態にあるもの
(B)高効率給湯器
①次世代型ソーラーシステムによる給湯器・・住宅の屋根などに設置し、太陽熱を利用する設備で、下記の条件に合致するもの
・強制循環方式であること
・集熱器と蓄熱槽が分離されているものであること
・集熱器の面積が3平方メートル以上であること
・補助熱源器が一次エネルギー比90%以上の熱利用効率であること
・財団法人ベターリビングによる優良住宅部品の認定を受けていること
・製造者等が7年以上の長期保証制度を有していること
②潜熱回収型給湯器(熱利用効率が90%以上)→(筆者注)いわゆる「エコジョーズ」と言われるガス給湯器で、高温排気から一次(顕熱)交換器で回収し切れなかった高温水蒸気を二次(潜熱)交換器に通して熱エネルギーを回収するもので、通常熱利用効率は90%以上になる。
③ヒートポンプ式給湯器(通年エネルギー消費効率が3.0以上のもの)→(筆者注)いわゆる「エコキュート」と言われる電気式給湯器で熱媒に二酸化炭素を使用している
④家庭用ガスコージェネレーションシステム(ガスエンジン方式、燃料電池方式)→(筆者注)いわゆる「エコウィル」と言われるガスエンジンによる発電・熱併用システムと、いわゆる「エネファーム」と言われるガスを利用した燃料電池による発電・熱併用システムがある。
(C)節電改修・・総額10万円以上の次に掲げる改修事業
①断熱窓・・複層ガラスへの交換、内窓の増設、窓の交換等
②高効率空調機・・統一省エネラベル制度最高評価のエアコン
③高効率照明・・高効率蛍光灯器具(統一省エネラベル制度最高評価のもの)、LED照明器具に変更するもの
(D)クリーンエネルギー自動車
①電気自動車
②プラグインハイブリッド自動車・・コンセントから差込プラグを用いて直接バッテリー充電できるハイブリッド自動車
(補助金額についてはここでは省略)
続きを読む

(広報ふじ5/5号 No.1031)
この中で若干判りにくい表現がありますが、市の広報なので、具体的な商品名やメーカー名を出しにくいためと思われます。
詳しくは市の環境総務課に問い合わせるのが適当ですが、筆者の理解するところで簡単な解説を加えて見たいと思います。
構成は
(1)事業者向け「中小企業者温暖化対策事業費補助金(新設)
・新エネルギー設備や省エネルギー設備の導入に対して補助金が交付されます。
①新エネルギー設備とは・・政令により指定された、太陽熱利用、地熱発電、風力発電、太陽光発電などを行うための設備で、外部へのエネルギー供給を行うもの→(筆者注)政令ではこの他に「雪氷熱利用」、「バイオマス発電」、「バイオマス熱利用」、「バイオマス燃料製造(アルコール燃料、バイオディーゼル、バイオガスなど)」、「塩分濃度差発電」、「温度差エネルギー」、「未利用水力を利用する水力発電(出力1000kw以下のものに限る)」などがあります。
②省エネルギー設備とは・・富士市環境アドバイザーによる(無料)診断、又は国・県が実施する無料省エネルギー診断に基づく設備
→(筆者注)無料診断を受けて省エネルギー設備と認定されたものが対象となるので、省エネ診断を受けることが必須要件。
・補助金の対象となる事業は次の通り
①温室効果ガス総排出量を10%以上削減する事業→(筆者注)上記いずれかの無料省エネ診断を受けると明らかになる。
②温室効果ガス排出削減量が年5トン以上の事業→(筆者注)上記と同じ
③売電を目的とする事業→(筆者注)自家消費目的のものは対象外
④富士市環境エネルギー推進協議会が推奨する機器を導入する事業→(筆者注)推奨されるには富士市に審査を申請し、審査の結果、「推奨機器」に認定される必要があります。
(補助金額についてはここでは省略)
(2)市民向け「市民温暖化対策事業費補助金(新設)
・補助金対象事業になるには次の「A」と「B,C,Dのいずれか」と組み合わせて実施する事業
(A)太陽光発電システム・・最大出力3kw以上で、発生した電気を電力会社へ供給できる状態にあるもの
(B)高効率給湯器
①次世代型ソーラーシステムによる給湯器・・住宅の屋根などに設置し、太陽熱を利用する設備で、下記の条件に合致するもの
・強制循環方式であること
・集熱器と蓄熱槽が分離されているものであること
・集熱器の面積が3平方メートル以上であること
・補助熱源器が一次エネルギー比90%以上の熱利用効率であること
・財団法人ベターリビングによる優良住宅部品の認定を受けていること
・製造者等が7年以上の長期保証制度を有していること
②潜熱回収型給湯器(熱利用効率が90%以上)→(筆者注)いわゆる「エコジョーズ」と言われるガス給湯器で、高温排気から一次(顕熱)交換器で回収し切れなかった高温水蒸気を二次(潜熱)交換器に通して熱エネルギーを回収するもので、通常熱利用効率は90%以上になる。
③ヒートポンプ式給湯器(通年エネルギー消費効率が3.0以上のもの)→(筆者注)いわゆる「エコキュート」と言われる電気式給湯器で熱媒に二酸化炭素を使用している
④家庭用ガスコージェネレーションシステム(ガスエンジン方式、燃料電池方式)→(筆者注)いわゆる「エコウィル」と言われるガスエンジンによる発電・熱併用システムと、いわゆる「エネファーム」と言われるガスを利用した燃料電池による発電・熱併用システムがある。
(C)節電改修・・総額10万円以上の次に掲げる改修事業
①断熱窓・・複層ガラスへの交換、内窓の増設、窓の交換等
②高効率空調機・・統一省エネラベル制度最高評価のエアコン
③高効率照明・・高効率蛍光灯器具(統一省エネラベル制度最高評価のもの)、LED照明器具に変更するもの
(D)クリーンエネルギー自動車
①電気自動車
②プラグインハイブリッド自動車・・コンセントから差込プラグを用いて直接バッテリー充電できるハイブリッド自動車
(補助金額についてはここでは省略)
続きを読む