2012年06月16日
家庭向け電力料金自由化の流れ
6月15日付日経新聞「ゼミナール:電力改革の論点④」欄で東京国際大学教授武石礼司氏の解説で「家庭向け電力料金自由化」の流れについて掲載されています。
契約電力が50kw以上の大口需要家向けは2000年に自由化されています(実際は種々の制約条件で普及はわずか)が、50kw未満の小口需要家(一般家庭含む)向けは安定供給を最重要視した電力会社10社の地域独占を前提とし、料金自由化は認められていません。
小口需要家向け電力料金の算定には公共料金の算定で一般的に使われる「総括原価方式」が採用されており、下記の算定式が用いられています。
電力料金収入=営業費+事業報酬ー控除収益
・営業費・・発送電設備建設維持費、購入電力料、燃料費(為替レート含む)、減価償却費、人件費等
・事業報酬・・事業資産の価値×一定比率(3%)(自由に使える利益ではなく資金調達に必要なコストに見合うものとの東電説明)
・控除収益・・他社販売電力料等
ここで問題となるのは「事業報酬」よりも「営業費」ではないかと思われます。事業に関わる全ての経費を営業費として計上し、電力料金を算出しているので、経費が膨らんでも、自らの利益が減らない仕組みになっているのです。民間企業では市場の原理に従って、利益が減ればリストラや経費節減等の自助努力をせざるを得ないのですが、電力会社の場合は地域独占の「安定供給」を担保として料金値上げをするわけです。このようなことから、電力料金値上げの発表でも「電力の安定供給は私達の責務であり、従って料金値上げは私達の権利」との東電社長の発言になるのでしょう。
このような現状を打開するため、経産省の電力システム改革専門委員会は5月、電力小売りを家庭まで含め全面的に自由化する方針で一致し、政府は電気事業法の改正案を早ければ13年の通常国会に提出し、14年度以降の実施を目指すとのことです。

(出所:OECD/IEAエネルギー価格年報 各国産業用・家庭用電気料金推移)
契約電力が50kw以上の大口需要家向けは2000年に自由化されています(実際は種々の制約条件で普及はわずか)が、50kw未満の小口需要家(一般家庭含む)向けは安定供給を最重要視した電力会社10社の地域独占を前提とし、料金自由化は認められていません。
小口需要家向け電力料金の算定には公共料金の算定で一般的に使われる「総括原価方式」が採用されており、下記の算定式が用いられています。
電力料金収入=営業費+事業報酬ー控除収益
・営業費・・発送電設備建設維持費、購入電力料、燃料費(為替レート含む)、減価償却費、人件費等
・事業報酬・・事業資産の価値×一定比率(3%)(自由に使える利益ではなく資金調達に必要なコストに見合うものとの東電説明)
・控除収益・・他社販売電力料等
ここで問題となるのは「事業報酬」よりも「営業費」ではないかと思われます。事業に関わる全ての経費を営業費として計上し、電力料金を算出しているので、経費が膨らんでも、自らの利益が減らない仕組みになっているのです。民間企業では市場の原理に従って、利益が減ればリストラや経費節減等の自助努力をせざるを得ないのですが、電力会社の場合は地域独占の「安定供給」を担保として料金値上げをするわけです。このようなことから、電力料金値上げの発表でも「電力の安定供給は私達の責務であり、従って料金値上げは私達の権利」との東電社長の発言になるのでしょう。
このような現状を打開するため、経産省の電力システム改革専門委員会は5月、電力小売りを家庭まで含め全面的に自由化する方針で一致し、政府は電気事業法の改正案を早ければ13年の通常国会に提出し、14年度以降の実施を目指すとのことです。

(出所:OECD/IEAエネルギー価格年報 各国産業用・家庭用電気料金推移)
先日、本ブログでも紹介した東京電力が開発中の「スマートメーター」はこの流れに対して一部逆行する仕様になっているとの指摘がなされているわけです。即ち電力の自由化がしにくいスマートメーターの仕様になっているとの指摘です。
ちなみに、東京電力の家庭向け電力供給量は全体の38%に対し利益は91%であることが明らかにされたニュースが5月24日に流れており、弱い立場の需要家にしわ寄せするこの様な事実が明らかになるにつれ、電力会社への不信感がつのるのは致し方ないことだと思います。
ちなみに、東京電力の家庭向け電力供給量は全体の38%に対し利益は91%であることが明らかにされたニュースが5月24日に流れており、弱い立場の需要家にしわ寄せするこの様な事実が明らかになるにつれ、電力会社への不信感がつのるのは致し方ないことだと思います。
Posted by 富士三合目 at 22:56│Comments(0)
│ビジネス





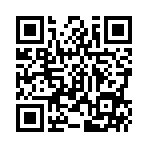



 MKビジネスサポート
MKビジネスサポート





