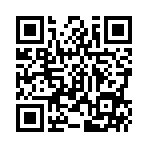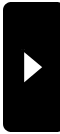2012年07月05日
日本卸電力取引所(JEPX)とは
一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)というものがあり、平成17年4月から卸電力市場を開設していましたが、今ひとつピンと来ない存在でした。それが、今夏の電力需給対策を受け、6月18日から「分散型・グリーン売電市場」を開設しました。
この市場は、自家用発電設備やコージェネ(熱電併用)発電設備等の小口の余剰電力を販売出来る市場として、売電量が一定でない発電(出なり発電と言うらしい)や、1000kw未満の電力も対象として、売り手が販売価格、販売量、売り条件(期間・平日曜日、インバランス(不均衡が生じた場合の調整)条件など)等を任意で設定できる市場とのこと。

(出所:電気新聞 卸電力市場)
続きを読む
この市場は、自家用発電設備やコージェネ(熱電併用)発電設備等の小口の余剰電力を販売出来る市場として、売電量が一定でない発電(出なり発電と言うらしい)や、1000kw未満の電力も対象として、売り手が販売価格、販売量、売り条件(期間・平日曜日、インバランス(不均衡が生じた場合の調整)条件など)等を任意で設定できる市場とのこと。

(出所:電気新聞 卸電力市場)
続きを読む
2012年07月03日
これからの電気事業者
新しいエネルギー社会の幕開けとなりそうな再生可能エネルギーの固定価格買取制度が始まりましたが、判り難いのが電気事業者の区分です。国内大手電力会社10社が圧倒的な強さで、競争相手を抑え込んできたので、今まで弱小電気事業者が束になっても対抗出来ず、余り話題にならなかったのですが、ここへ来て、少し状況が変わりつつある様です。
電気事業者の区分としては下記の如くなっています。
①一般電気事業者・・東京電力等の大手10社で、一般(不特定多数)の需要に応じて電気を供給する者。一般への電気供給は、一般電気事業者しか行えないことになっている。
②卸電気事業者・・一般電気事業者に電気を供給する事業者で、200万kw超の発電設備を有する者。現在、「電源開発」、「日本原子力発電」の2社のみ。
③卸供給事業者・・一般電気事業者に電気を供給する「卸電気事業者」以外の者で、一般電気事業者と10年以上にわたり1000kw超の供給契約、もしくは5年以上にわたり10万kw超の供給契約を交わしている者(IPP、独立発電事業者:コスモ石油など)
④新電力(PPS)・・契約電力が50kw以上の需要家に対して一般電気事業者が有する電線路を通じて電力供給を行う事業者。小売自由化部門への新規参入者。「特定規模電気事業者」と言う。現在事業開始予定者を含め60社)
⑤特定電気事業者・・限定される区域に対し、自らの発電設備や電線路を用いて電気供給を行う事業者。東日本旅客鉄道、六本木エネルギーサービス、諏訪エネルギーサービスなど。
⑥特定供給・・供給者、需要者間の関係で、需要家保護の必要性の低い密接な関係(生産工程、資本関係、人的関係)を有する者の間での電力供給(本社工場と子会社工場間での電力供給等で東京ガスなど)
以上の6種の電気事業者を良く見ると、②、③はいわば①の大手10社の下請けのような存在で、一般への波及効果は小さい。これからの新しいエネルギー社会に影響力のあるのは、④、⑤、⑥で、6月18日から1000kw未満の「小口電力」を売買する「分散型・グリーン売電市場」がスタートしています。

(出所:日本経済新聞)
続きを読む
電気事業者の区分としては下記の如くなっています。
①一般電気事業者・・東京電力等の大手10社で、一般(不特定多数)の需要に応じて電気を供給する者。一般への電気供給は、一般電気事業者しか行えないことになっている。
②卸電気事業者・・一般電気事業者に電気を供給する事業者で、200万kw超の発電設備を有する者。現在、「電源開発」、「日本原子力発電」の2社のみ。
③卸供給事業者・・一般電気事業者に電気を供給する「卸電気事業者」以外の者で、一般電気事業者と10年以上にわたり1000kw超の供給契約、もしくは5年以上にわたり10万kw超の供給契約を交わしている者(IPP、独立発電事業者:コスモ石油など)
④新電力(PPS)・・契約電力が50kw以上の需要家に対して一般電気事業者が有する電線路を通じて電力供給を行う事業者。小売自由化部門への新規参入者。「特定規模電気事業者」と言う。現在事業開始予定者を含め60社)
⑤特定電気事業者・・限定される区域に対し、自らの発電設備や電線路を用いて電気供給を行う事業者。東日本旅客鉄道、六本木エネルギーサービス、諏訪エネルギーサービスなど。
⑥特定供給・・供給者、需要者間の関係で、需要家保護の必要性の低い密接な関係(生産工程、資本関係、人的関係)を有する者の間での電力供給(本社工場と子会社工場間での電力供給等で東京ガスなど)
以上の6種の電気事業者を良く見ると、②、③はいわば①の大手10社の下請けのような存在で、一般への波及効果は小さい。これからの新しいエネルギー社会に影響力のあるのは、④、⑤、⑥で、6月18日から1000kw未満の「小口電力」を売買する「分散型・グリーン売電市場」がスタートしています。

(出所:日本経済新聞)
続きを読む
2012年06月16日
家庭向け電力料金自由化の流れ
6月15日付日経新聞「ゼミナール:電力改革の論点④」欄で東京国際大学教授武石礼司氏の解説で「家庭向け電力料金自由化」の流れについて掲載されています。
契約電力が50kw以上の大口需要家向けは2000年に自由化されています(実際は種々の制約条件で普及はわずか)が、50kw未満の小口需要家(一般家庭含む)向けは安定供給を最重要視した電力会社10社の地域独占を前提とし、料金自由化は認められていません。
小口需要家向け電力料金の算定には公共料金の算定で一般的に使われる「総括原価方式」が採用されており、下記の算定式が用いられています。
電力料金収入=営業費+事業報酬ー控除収益
・営業費・・発送電設備建設維持費、購入電力料、燃料費(為替レート含む)、減価償却費、人件費等
・事業報酬・・事業資産の価値×一定比率(3%)(自由に使える利益ではなく資金調達に必要なコストに見合うものとの東電説明)
・控除収益・・他社販売電力料等
ここで問題となるのは「事業報酬」よりも「営業費」ではないかと思われます。事業に関わる全ての経費を営業費として計上し、電力料金を算出しているので、経費が膨らんでも、自らの利益が減らない仕組みになっているのです。民間企業では市場の原理に従って、利益が減ればリストラや経費節減等の自助努力をせざるを得ないのですが、電力会社の場合は地域独占の「安定供給」を担保として料金値上げをするわけです。このようなことから、電力料金値上げの発表でも「電力の安定供給は私達の責務であり、従って料金値上げは私達の権利」との東電社長の発言になるのでしょう。
このような現状を打開するため、経産省の電力システム改革専門委員会は5月、電力小売りを家庭まで含め全面的に自由化する方針で一致し、政府は電気事業法の改正案を早ければ13年の通常国会に提出し、14年度以降の実施を目指すとのことです。

(出所:OECD/IEAエネルギー価格年報 各国産業用・家庭用電気料金推移) 続きを読む
契約電力が50kw以上の大口需要家向けは2000年に自由化されています(実際は種々の制約条件で普及はわずか)が、50kw未満の小口需要家(一般家庭含む)向けは安定供給を最重要視した電力会社10社の地域独占を前提とし、料金自由化は認められていません。
小口需要家向け電力料金の算定には公共料金の算定で一般的に使われる「総括原価方式」が採用されており、下記の算定式が用いられています。
電力料金収入=営業費+事業報酬ー控除収益
・営業費・・発送電設備建設維持費、購入電力料、燃料費(為替レート含む)、減価償却費、人件費等
・事業報酬・・事業資産の価値×一定比率(3%)(自由に使える利益ではなく資金調達に必要なコストに見合うものとの東電説明)
・控除収益・・他社販売電力料等
ここで問題となるのは「事業報酬」よりも「営業費」ではないかと思われます。事業に関わる全ての経費を営業費として計上し、電力料金を算出しているので、経費が膨らんでも、自らの利益が減らない仕組みになっているのです。民間企業では市場の原理に従って、利益が減ればリストラや経費節減等の自助努力をせざるを得ないのですが、電力会社の場合は地域独占の「安定供給」を担保として料金値上げをするわけです。このようなことから、電力料金値上げの発表でも「電力の安定供給は私達の責務であり、従って料金値上げは私達の権利」との東電社長の発言になるのでしょう。
このような現状を打開するため、経産省の電力システム改革専門委員会は5月、電力小売りを家庭まで含め全面的に自由化する方針で一致し、政府は電気事業法の改正案を早ければ13年の通常国会に提出し、14年度以降の実施を目指すとのことです。

(出所:OECD/IEAエネルギー価格年報 各国産業用・家庭用電気料金推移) 続きを読む
2012年06月14日
レアアースの輸入量激減
今年1~4月の中国からのレアアース輸入量は昨年同期比70%減となった模様。原因は日本企業の在庫量確保と「脱レアアース技術」の開発進展によるものと言われています。使用量減に伴って価格も前年7月の最高値と比較すると70%ダウンとなっているようです。
ネオジムやジスプロシウム等を含まない高性能永久磁石の開発が急゚ッチで進んでおり、産出国の中国の輸出政策に振り回されなくなることが期待されます。

(出所:日経新聞)
ネオジムやジスプロシウム等を含まない高性能永久磁石の開発が急゚ッチで進んでおり、産出国の中国の輸出政策に振り回されなくなることが期待されます。

(出所:日経新聞)
2012年06月01日
「選択と集中」のウソ
最近の日経新聞に興味深い記事が二つ掲載されていました。
一つは編集委員大西康之氏の署名記事「経営の視点」(選択と集中のウソ)です。
米国の1950年代における代表的な家電メーカーでテレビの技術革新に貢献した「ゼニス社」と「RCA社」が1980年代には「選択と集中」の名のもとにリストラを続けた結果、エレクトロニクス産業の表舞台から姿を消し、現在はゼニスは韓国LG電子、RCAは仏トムソンの1ブランドになっている。氏は1980年代にゼニス社とRCA社が取った行動は、現在の日本の大手家電メーカーの取っている行動にそっくりだと言われる。
安く大量に作ることが得意だった当時の日本メーカーとの競合を避け、「次世代技術」に集中した。やがて両社からの生産委託で力をつけた日本メーカーに、世界市場を奪われ、体力を失ったため、虎の子の次世代技術を市場に広めることが出来なかった。米企業が道をつけた技術で稼いだのは日本企業だった。
あのころの日本メーカーを韓国、台湾メーカー、米メーカーを日本メーカーに置き換えればそのまま現代の構図になる。今の日本の電機大手は「選択と集中」の名の下に「撤退」を繰り返しているように見える。「新たな投資の決断」を伴わない撤退を、安易に「選択と集中」と呼ぶべきではない。
「撤退」は固定費の削減で一時的な増益につながるが、それだけでは事業規模が縮小し、成長が止まる。持続的に成長するために経営者は「投資の決断」を下さなくてはならない。 「選択と集中」を唱えたのは経営学者のピータードラッガーで、それを実践したのが「ゼネラルエレクトリック(GE)」のジャック・ウェルチ元会長とされる。ウェルチ氏が「選択と集中」で売却したのが、当時GE傘下のRCA社である。撤退を繰り返したRCAは、ウェルチ氏に捨てられた。その後、GEは撤退に見合う投資で復活した。・・以上耳の痛い話である。

(出所:ウィキペディア GE社の航空機エンジン) 続きを読む
一つは編集委員大西康之氏の署名記事「経営の視点」(選択と集中のウソ)です。
米国の1950年代における代表的な家電メーカーでテレビの技術革新に貢献した「ゼニス社」と「RCA社」が1980年代には「選択と集中」の名のもとにリストラを続けた結果、エレクトロニクス産業の表舞台から姿を消し、現在はゼニスは韓国LG電子、RCAは仏トムソンの1ブランドになっている。氏は1980年代にゼニス社とRCA社が取った行動は、現在の日本の大手家電メーカーの取っている行動にそっくりだと言われる。
安く大量に作ることが得意だった当時の日本メーカーとの競合を避け、「次世代技術」に集中した。やがて両社からの生産委託で力をつけた日本メーカーに、世界市場を奪われ、体力を失ったため、虎の子の次世代技術を市場に広めることが出来なかった。米企業が道をつけた技術で稼いだのは日本企業だった。
あのころの日本メーカーを韓国、台湾メーカー、米メーカーを日本メーカーに置き換えればそのまま現代の構図になる。今の日本の電機大手は「選択と集中」の名の下に「撤退」を繰り返しているように見える。「新たな投資の決断」を伴わない撤退を、安易に「選択と集中」と呼ぶべきではない。
「撤退」は固定費の削減で一時的な増益につながるが、それだけでは事業規模が縮小し、成長が止まる。持続的に成長するために経営者は「投資の決断」を下さなくてはならない。 「選択と集中」を唱えたのは経営学者のピータードラッガーで、それを実践したのが「ゼネラルエレクトリック(GE)」のジャック・ウェルチ元会長とされる。ウェルチ氏が「選択と集中」で売却したのが、当時GE傘下のRCA社である。撤退を繰り返したRCAは、ウェルチ氏に捨てられた。その後、GEは撤退に見合う投資で復活した。・・以上耳の痛い話である。

(出所:ウィキペディア GE社の航空機エンジン) 続きを読む