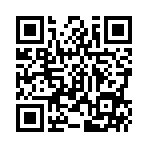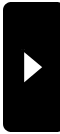2012年06月27日
「スマートメーター」と「スマートハウス」
最近新聞を見ると、「スマートメーター」や「スマートハウス」、更には「スマートグリッド」、「スマートシティ」などなど「スマート」の付く言葉が飛び交っていますが、その基になるのは「スマートメーター」で、双方向の通信機能を持つ特別な電力計が必要です。
「スマートメーター」については、東京電力が開発中のものを、未だ余り賢くない(スマートでない)例として先日、本ブログでも紹介しましたが、このスマートメーターが文字通り賢くなってくれなくては困るのです。
「スマートメーター」の役割は、これを設置すれば、パソコンや携帯電話でリアルタイムの電力消費量などが確認でき、遠隔操作で家電製品のスイッチをオン・オフでき、太陽光発電を制御できると言うものです。
「スマートメーター」の各家庭への導入は、地球温暖化防止に熱心なヨーロッパが先行していて、イタリアやスウェーデン等では既に対象となるほぼ全ての家庭で導入が終わっているとのこと。
各国のスマートメーターの導入計画は下記の如くなっています。(6/27日経新聞「ゼミナール:電力改革の論点⑪」)
①全家庭に導入済み・・イタリア、スウェーデンなど
②2015年までに全需要家に導入・・米カリフォルニア州、豪ビクトリア州、フィンランド、
③2017年までに総需要量の8割・・日本
④2018年までに全需要家・・スペイン
⑤2020年までに全需要家・・英国・中国・韓国
⑥2020年までに全需要家の8割・・欧州連合(EU)加盟国

(出所:You Tube スマートハウスのイメージ図) 続きを読む
「スマートメーター」については、東京電力が開発中のものを、未だ余り賢くない(スマートでない)例として先日、本ブログでも紹介しましたが、このスマートメーターが文字通り賢くなってくれなくては困るのです。
「スマートメーター」の役割は、これを設置すれば、パソコンや携帯電話でリアルタイムの電力消費量などが確認でき、遠隔操作で家電製品のスイッチをオン・オフでき、太陽光発電を制御できると言うものです。
「スマートメーター」の各家庭への導入は、地球温暖化防止に熱心なヨーロッパが先行していて、イタリアやスウェーデン等では既に対象となるほぼ全ての家庭で導入が終わっているとのこと。
各国のスマートメーターの導入計画は下記の如くなっています。(6/27日経新聞「ゼミナール:電力改革の論点⑪」)
①全家庭に導入済み・・イタリア、スウェーデンなど
②2015年までに全需要家に導入・・米カリフォルニア州、豪ビクトリア州、フィンランド、
③2017年までに総需要量の8割・・日本
④2018年までに全需要家・・スペイン
⑤2020年までに全需要家・・英国・中国・韓国
⑥2020年までに全需要家の8割・・欧州連合(EU)加盟国

(出所:You Tube スマートハウスのイメージ図) 続きを読む
2012年06月24日
進みつつある「排熱利用」の研究
普段の生活で何気なく捨てている熱エネルギーの利用研究が進んでいるとのこと。(6月24日付日経新聞)
排熱とは、熱は完全に使い切るのは難しいので、余った熱が利用されずに「排熱」として出てくる。例えば、ゴミ焼却や工場の稼動に伴う熱、自動車から出る排ガス、エアコン使用時に外に放出される熱風など、人間の活動によって出る熱を排熱と呼ぶ場合が多い。排熱はこれまで十分に活用されてきたとは言い難く、それは、熱の再利用を可能にする技術が足りなかった点に加え、熱を使い回す発想が乏しかったためと言われる。最近これらの排熱利用技術が新エネルギーの一つとして注目を集めているとのこと。(前記日経新聞)
大阪市の千島下水処理場の実証試験は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と大阪市立大学、総合設備コンサルタント、中央復建コンサルタンツ、関西電力のグループが取り組んでいます。下水は夏は気温より2~3℃低く、冬は10℃以上高いので、熱は加熱に、冷気は冷却に利用でき、熱交換やヒートポンプを使い、下水と気温の温度差を給湯や冷暖房に生かすことが出来るとのことです。
ところで、同じような下水の排熱利用は東京都下水道局でもかなり前から行われており、東京都下水道局のホームページに出ています。

(出所:東京都下水道局ホームページ 「夏冬の下水温度と気温の差」)
東京都下水道局では下水の排熱利用システムを「アーバンヒート」と呼び、第1号は昭和62年1月落合水再生センターで設置されています。
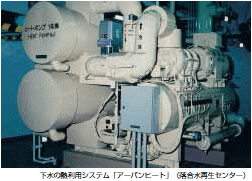
(出所:東京都水道局ホームページ 落合水再生センターの「アーバンヒート第1号」)
続きを読む
排熱とは、熱は完全に使い切るのは難しいので、余った熱が利用されずに「排熱」として出てくる。例えば、ゴミ焼却や工場の稼動に伴う熱、自動車から出る排ガス、エアコン使用時に外に放出される熱風など、人間の活動によって出る熱を排熱と呼ぶ場合が多い。排熱はこれまで十分に活用されてきたとは言い難く、それは、熱の再利用を可能にする技術が足りなかった点に加え、熱を使い回す発想が乏しかったためと言われる。最近これらの排熱利用技術が新エネルギーの一つとして注目を集めているとのこと。(前記日経新聞)
大阪市の千島下水処理場の実証試験は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と大阪市立大学、総合設備コンサルタント、中央復建コンサルタンツ、関西電力のグループが取り組んでいます。下水は夏は気温より2~3℃低く、冬は10℃以上高いので、熱は加熱に、冷気は冷却に利用でき、熱交換やヒートポンプを使い、下水と気温の温度差を給湯や冷暖房に生かすことが出来るとのことです。
ところで、同じような下水の排熱利用は東京都下水道局でもかなり前から行われており、東京都下水道局のホームページに出ています。

(出所:東京都下水道局ホームページ 「夏冬の下水温度と気温の差」)
東京都下水道局では下水の排熱利用システムを「アーバンヒート」と呼び、第1号は昭和62年1月落合水再生センターで設置されています。
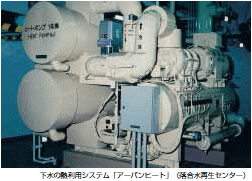
(出所:東京都水道局ホームページ 落合水再生センターの「アーバンヒート第1号」)
続きを読む
2012年06月13日
賢さの足りない?「スマートメーター」
電力の効率的利用の切り札として期待されている次世代電力計「スマートメーター」ではありますが、どうやら電力会社(東電)の開発しているスマート(直訳:賢い・気の利いた)メーターは実は余り賢くない(もしかしたら「抜け目の無い」)仕様になっていると指摘されています。
東京電力のスマートメーターの主な仕様は
1)高層マンションや地下街、山間部でも対応可能な通信方法
2)無線、有線などでデータを送信し、検針の人手を省力化
3)30分間積算した電力使用量のデータを送信
4)通信データの暗号化などでデータを送信
5)インターネットで普及している通信手段「TCP/IP」は実装せず
となっており、一見問題なさそうに見えますが、どの部分がスマートで無い(賢くない)と指摘されているのでしょうか。それは以下の3つの課題です。
①30分ごとのデータ送信
・これから注力される新エネルギー(太陽光・風力発電等)は発電出力の変動が大きく、リアルタイムで調整する必要があり、30分ごとでは対応できない。→新電力の参入障壁となる
②先行している関西電力等の他の電力会社のスマートメーターとの仕様統一をする考えはなく、独立仕様となっており、互換性がない。(いわゆるガラパゴス化となる)
・これはスマートメーターのコストアップとなり、又、互換性がないことから価格競争が無いので、使用者(消費者)にとって選択の余地なく高い物を否応なく押し付けられることになる。(設置費は東電が負担しても、その費用は電力料金にハネ返る)
→これは電力会社の地域独占思想に基づく排他的なものと言われている。
③インターネットで普及している通信手段(TCP/IP)を実装していないので専用回線となる。
・電力使用データは重要な個人情報であり、又、インターネット回線はウィルス進入リスクがあるゆえセキュリティー面を重視したものと説明されていて、それ自体は大切なことではあるが、一方では新電力(特定規模電気事業者:PPS)の参入障壁になる。即ち、インターネット回線が使用できなければ、PPSは東電経由でデータを入手するか、東電仕様でないメーターを取り付ける必要がある。→新電力導入に逆行するものとなる。

(出所:Tech-On!ホームページ 「スマートメーターのコンセプト」)
続きを読む
東京電力のスマートメーターの主な仕様は
1)高層マンションや地下街、山間部でも対応可能な通信方法
2)無線、有線などでデータを送信し、検針の人手を省力化
3)30分間積算した電力使用量のデータを送信
4)通信データの暗号化などでデータを送信
5)インターネットで普及している通信手段「TCP/IP」は実装せず
となっており、一見問題なさそうに見えますが、どの部分がスマートで無い(賢くない)と指摘されているのでしょうか。それは以下の3つの課題です。
①30分ごとのデータ送信
・これから注力される新エネルギー(太陽光・風力発電等)は発電出力の変動が大きく、リアルタイムで調整する必要があり、30分ごとでは対応できない。→新電力の参入障壁となる
②先行している関西電力等の他の電力会社のスマートメーターとの仕様統一をする考えはなく、独立仕様となっており、互換性がない。(いわゆるガラパゴス化となる)
・これはスマートメーターのコストアップとなり、又、互換性がないことから価格競争が無いので、使用者(消費者)にとって選択の余地なく高い物を否応なく押し付けられることになる。(設置費は東電が負担しても、その費用は電力料金にハネ返る)
→これは電力会社の地域独占思想に基づく排他的なものと言われている。
③インターネットで普及している通信手段(TCP/IP)を実装していないので専用回線となる。
・電力使用データは重要な個人情報であり、又、インターネット回線はウィルス進入リスクがあるゆえセキュリティー面を重視したものと説明されていて、それ自体は大切なことではあるが、一方では新電力(特定規模電気事業者:PPS)の参入障壁になる。即ち、インターネット回線が使用できなければ、PPSは東電経由でデータを入手するか、東電仕様でないメーターを取り付ける必要がある。→新電力導入に逆行するものとなる。

(出所:Tech-On!ホームページ 「スマートメーターのコンセプト」)
続きを読む
2012年05月31日
ネガワット取引とは?
関西電力では今夏の節電要請期間(7月2日~9月7日)に、法人向け電力需要抑制策の一環として、管内の企業が節電した電力を入札で買い取る「ネガワット取引」制度を国内電力会社としては初めて導入するとのことです。
この「ネガワット取引」と言う聞き馴れない制度は成功すれば、夏場や、冬場の「電力需給」の切り札として国内の他地域に広がる可能性が高いと言われています。

(出所:Amazon書籍広告)
では、「ネガワット取引」とは一体どのような制度でしょうか。
「ネガワット」は企業が省エネ・節電によって使用しなかった電力を指し、省エネ・節電の取組みは発電所の建設と同様の効果を生み、いわば「節電所」と見なす考え方で、この使用しなかった電力を電力会社が入札によって買い上げる制度です。米国で考案され、電力逼迫時に活用されている制度とのこと。これならば、省エネ・節電した企業は使わなかった分、電力料金の節約になり、且つそれによって余った電力を入札価格で電力会社に売ることが出来、一石二鳥で省エネ・節電努力のモティベーションが高まると言う仕組み。(但し、入札なので、最安値を入札した企業の電力が買い上げられることになる。又、もし、落札した企業が約束通り節電できなかった場合にはペナルティが課せられるので、いい加減な気持ちではできません。)それでも、否応なしの計画停電や、ピーク時電力料金をべらぼうな高価格にして強制的に使わせないと言う、高圧的な全く芸のないやり方と比べればかなり優れた方法ではないでしょうか。
続きを読む
この「ネガワット取引」と言う聞き馴れない制度は成功すれば、夏場や、冬場の「電力需給」の切り札として国内の他地域に広がる可能性が高いと言われています。

(出所:Amazon書籍広告)
では、「ネガワット取引」とは一体どのような制度でしょうか。
「ネガワット」は企業が省エネ・節電によって使用しなかった電力を指し、省エネ・節電の取組みは発電所の建設と同様の効果を生み、いわば「節電所」と見なす考え方で、この使用しなかった電力を電力会社が入札によって買い上げる制度です。米国で考案され、電力逼迫時に活用されている制度とのこと。これならば、省エネ・節電した企業は使わなかった分、電力料金の節約になり、且つそれによって余った電力を入札価格で電力会社に売ることが出来、一石二鳥で省エネ・節電努力のモティベーションが高まると言う仕組み。(但し、入札なので、最安値を入札した企業の電力が買い上げられることになる。又、もし、落札した企業が約束通り節電できなかった場合にはペナルティが課せられるので、いい加減な気持ちではできません。)それでも、否応なしの計画停電や、ピーク時電力料金をべらぼうな高価格にして強制的に使わせないと言う、高圧的な全く芸のないやり方と比べればかなり優れた方法ではないでしょうか。
続きを読む
2012年04月14日
HEMSとは?
HEMSとは「ホーム・エネルギー・マネジメント・システム」のことで、IT(情報技術)によって住まいをスマートハウス(賢い住宅)にすることだそうです。最近急速に進化している最先端省エネ住宅で、住宅メーカーはこのHEMSを搭載することによって「ゼロエネルギー住宅」を顧客に提供することを目指しているとのことです。

(出所:資源エネルギー庁「エネルギー白書(2006年度版)」 HEMSの概要)
イメージとしては、家庭内の各種家電製品、太陽光発電システム、蓄電池などの創エネ、蓄エネ設備等と外部の電力網、情報網とを繋げたエネルギーの管理システムで、家庭内のエネルギーを管理し、最適化を実現するシステムです。
続きを読む

(出所:資源エネルギー庁「エネルギー白書(2006年度版)」 HEMSの概要)
イメージとしては、家庭内の各種家電製品、太陽光発電システム、蓄電池などの創エネ、蓄エネ設備等と外部の電力網、情報網とを繋げたエネルギーの管理システムで、家庭内のエネルギーを管理し、最適化を実現するシステムです。
続きを読む