2012年06月01日
「選択と集中」のウソ
最近の日経新聞に興味深い記事が二つ掲載されていました。
一つは編集委員大西康之氏の署名記事「経営の視点」(選択と集中のウソ)です。
米国の1950年代における代表的な家電メーカーでテレビの技術革新に貢献した「ゼニス社」と「RCA社」が1980年代には「選択と集中」の名のもとにリストラを続けた結果、エレクトロニクス産業の表舞台から姿を消し、現在はゼニスは韓国LG電子、RCAは仏トムソンの1ブランドになっている。氏は1980年代にゼニス社とRCA社が取った行動は、現在の日本の大手家電メーカーの取っている行動にそっくりだと言われる。
安く大量に作ることが得意だった当時の日本メーカーとの競合を避け、「次世代技術」に集中した。やがて両社からの生産委託で力をつけた日本メーカーに、世界市場を奪われ、体力を失ったため、虎の子の次世代技術を市場に広めることが出来なかった。米企業が道をつけた技術で稼いだのは日本企業だった。
あのころの日本メーカーを韓国、台湾メーカー、米メーカーを日本メーカーに置き換えればそのまま現代の構図になる。今の日本の電機大手は「選択と集中」の名の下に「撤退」を繰り返しているように見える。「新たな投資の決断」を伴わない撤退を、安易に「選択と集中」と呼ぶべきではない。
「撤退」は固定費の削減で一時的な増益につながるが、それだけでは事業規模が縮小し、成長が止まる。持続的に成長するために経営者は「投資の決断」を下さなくてはならない。 「選択と集中」を唱えたのは経営学者のピータードラッガーで、それを実践したのが「ゼネラルエレクトリック(GE)」のジャック・ウェルチ元会長とされる。ウェルチ氏が「選択と集中」で売却したのが、当時GE傘下のRCA社である。撤退を繰り返したRCAは、ウェルチ氏に捨てられた。その後、GEは撤退に見合う投資で復活した。・・以上耳の痛い話である。

(出所:ウィキペディア GE社の航空機エンジン)
一つは編集委員大西康之氏の署名記事「経営の視点」(選択と集中のウソ)です。
米国の1950年代における代表的な家電メーカーでテレビの技術革新に貢献した「ゼニス社」と「RCA社」が1980年代には「選択と集中」の名のもとにリストラを続けた結果、エレクトロニクス産業の表舞台から姿を消し、現在はゼニスは韓国LG電子、RCAは仏トムソンの1ブランドになっている。氏は1980年代にゼニス社とRCA社が取った行動は、現在の日本の大手家電メーカーの取っている行動にそっくりだと言われる。
安く大量に作ることが得意だった当時の日本メーカーとの競合を避け、「次世代技術」に集中した。やがて両社からの生産委託で力をつけた日本メーカーに、世界市場を奪われ、体力を失ったため、虎の子の次世代技術を市場に広めることが出来なかった。米企業が道をつけた技術で稼いだのは日本企業だった。
あのころの日本メーカーを韓国、台湾メーカー、米メーカーを日本メーカーに置き換えればそのまま現代の構図になる。今の日本の電機大手は「選択と集中」の名の下に「撤退」を繰り返しているように見える。「新たな投資の決断」を伴わない撤退を、安易に「選択と集中」と呼ぶべきではない。
「撤退」は固定費の削減で一時的な増益につながるが、それだけでは事業規模が縮小し、成長が止まる。持続的に成長するために経営者は「投資の決断」を下さなくてはならない。 「選択と集中」を唱えたのは経営学者のピータードラッガーで、それを実践したのが「ゼネラルエレクトリック(GE)」のジャック・ウェルチ元会長とされる。ウェルチ氏が「選択と集中」で売却したのが、当時GE傘下のRCA社である。撤退を繰り返したRCAは、ウェルチ氏に捨てられた。その後、GEは撤退に見合う投資で復活した。・・以上耳の痛い話である。

(出所:ウィキペディア GE社の航空機エンジン)
もう一つは経済教室「ものづくり再生の視点㊥」(経営者は現場の力結集を)と題する東京大学准教授新宅純二郎氏の記事である。
業績悪化に苦しみ経営再生を図ろうとする日本の大企業の姿を見ていると、日本の製造業が米国に進出し、日米貿易摩擦を引き起こした1980年代の米国製造業の姿を思い起こす。当時の米国企業の姿は、韓国、台湾、中国企業との競争で劣勢に立たされている今日の日本企業に良く似ている。
米国企業の多くは日本企業の脅威に対処するため、競争の激しい分野から撤退したり、売却したりする一方で、海外からの競争圧力の少ない新しい事業分野に集中しようとした。しかし、その多くは失敗に終り、本業に回帰して再生を進めた企業も少なくない。その例として「USスティール」や「IBM」がある。
当時の経営戦略の分野での大きな変化は、全社レベルの多角化戦略から、個別事業分野での競争優位を徹底的に議論する戦略へとシフトしたことであり、背景には米ハーバード大学のマイケル・ポーター教授と言う優れた研究者が出たことに加え、米国企業の認識が変わったことにある。
目前の競争を回避して不慣れな新規事業分野に進出してもなかなか業績は改善しない。資源蓄積の多い既存事業での競争優位を作るために全力を注ぐ。あるいは新規事業についても、そこでの競争戦略を徹底して検討・実行すべきだとの認識が出てきた。「個別事業で1位か2位になれ」と言うジャック・ウェルチ氏による米GEの改革はまさにそれである。

(出所:ウィキペディア GE社の医療用MRI)
翻って、現在苦境に陥っている日本の電機メーカーを見ていると後ろ向きの事業リストラに関する意思決定に関わる動きが多い。
とりわけ、「苦境に立っている事業から思い切って早く撤退すべし」と言う議論は極めて危険である。ある事業から撤退するのは、売却・撤退により得られる経営資源を振り向けるべき事業が明確な場合である・・。→ここまでは前記の大西氏の書かれた内容と殆ど同じと言えよう。
筆者は更に、日本企業のものづくり現場を多数見て、「ものづくり現場力」は決して弱いとは思えない。問題は強い現場力を生かし切れていない経営に問題があると言われる。更には、経営者の役割は、社内の有用な資源を売ることではなく、有効に活用することにある。各部門の現場の力を結集して、全体としての成果に結びつけていくことである。部門間分業に任せるだけならアウトソーシング(外部委託)した方がよいと言うことになろう。部門間をいかにつなげて協業する組織をつくり上げるかが、苦境に立った企業の経営者の重要な使命である。・・以上手厳しく、又示唆に富んだ話であると思います。
業績悪化に苦しみ経営再生を図ろうとする日本の大企業の姿を見ていると、日本の製造業が米国に進出し、日米貿易摩擦を引き起こした1980年代の米国製造業の姿を思い起こす。当時の米国企業の姿は、韓国、台湾、中国企業との競争で劣勢に立たされている今日の日本企業に良く似ている。
米国企業の多くは日本企業の脅威に対処するため、競争の激しい分野から撤退したり、売却したりする一方で、海外からの競争圧力の少ない新しい事業分野に集中しようとした。しかし、その多くは失敗に終り、本業に回帰して再生を進めた企業も少なくない。その例として「USスティール」や「IBM」がある。
当時の経営戦略の分野での大きな変化は、全社レベルの多角化戦略から、個別事業分野での競争優位を徹底的に議論する戦略へとシフトしたことであり、背景には米ハーバード大学のマイケル・ポーター教授と言う優れた研究者が出たことに加え、米国企業の認識が変わったことにある。
目前の競争を回避して不慣れな新規事業分野に進出してもなかなか業績は改善しない。資源蓄積の多い既存事業での競争優位を作るために全力を注ぐ。あるいは新規事業についても、そこでの競争戦略を徹底して検討・実行すべきだとの認識が出てきた。「個別事業で1位か2位になれ」と言うジャック・ウェルチ氏による米GEの改革はまさにそれである。

(出所:ウィキペディア GE社の医療用MRI)
翻って、現在苦境に陥っている日本の電機メーカーを見ていると後ろ向きの事業リストラに関する意思決定に関わる動きが多い。
とりわけ、「苦境に立っている事業から思い切って早く撤退すべし」と言う議論は極めて危険である。ある事業から撤退するのは、売却・撤退により得られる経営資源を振り向けるべき事業が明確な場合である・・。→ここまでは前記の大西氏の書かれた内容と殆ど同じと言えよう。
筆者は更に、日本企業のものづくり現場を多数見て、「ものづくり現場力」は決して弱いとは思えない。問題は強い現場力を生かし切れていない経営に問題があると言われる。更には、経営者の役割は、社内の有用な資源を売ることではなく、有効に活用することにある。各部門の現場の力を結集して、全体としての成果に結びつけていくことである。部門間分業に任せるだけならアウトソーシング(外部委託)した方がよいと言うことになろう。部門間をいかにつなげて協業する組織をつくり上げるかが、苦境に立った企業の経営者の重要な使命である。・・以上手厳しく、又示唆に富んだ話であると思います。
Posted by 富士三合目 at 01:31│Comments(0)
│ビジネス





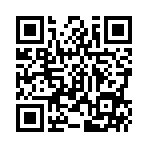



 MKビジネスサポート
MKビジネスサポート





