2012年05月12日
BSフジのプライムニュース「太陽の異変」を見て
昨夜(5月11日)20:00~21:55、BSフジのプライムニュースで「太陽に異変、地球寒冷化の可能性」を見ました、これは、本ブログで5/6付で紹介した立花隆さんの文藝春秋5月号の記事「太陽の謎」に関連する内容のもので、ゲストは国立天文台常田佐久教授と広島大学大学院長沼毅准教授でした。
常田教授のお話は今年4月19日国立天文台で発表した、「 『ひので』 による今回の観測の意義と最近の太陽活動について」の内容によるものです。「ひので」はわが国が世界に誇る国産人工衛星で、太陽(特に黒点)観測を目的とし、2006年9月に打ち上げられ現在も稼働中で、時々刻々と観測データを地球に送り続けています。
番組の前編はこの太陽活動の観測結果による異変についての解説で、その異変とは、5/6の本ブログで紹介した内容と同様です。(黒点増減周期と太陽南極、北極の磁極反転の異変)
太陽黒点の増減を観測し始めた400年前のガリレオ・ガリレイの時代から、周期に異変のあった時期は過去2回あり、1810年頃と1680年頃で、この時は小氷期でロンドンのテムズ川が氷結したり、日本でも冷害による大飢饉があったとの記録が残っているようです。

(出所:英ウィキペディア テムズ川凍結画1814年)

(出所:英ウィキペディア テムズ川凍結画1683~1684年)
そこで、ここからは科学的推論になりますが、現在の黒点の増減の様子が過去2回の小氷期に似ており、従って近未来に小氷期が来るであろうと言うものです。又、寒冷化の原因は、太陽から来る熱・光エネルギーそのものが弱まるのではなく、磁力線が弱まることによって磁力線のバリヤーが弱まり、宇宙から地球に降り注ぐ宇宙線が強くなって、雲の核になる物質が増え、それによって雲が増え、そのために太陽エネルギー(熱・光)が遮られて寒冷化するという訳です。
常田教授のお話は今年4月19日国立天文台で発表した、「 『ひので』 による今回の観測の意義と最近の太陽活動について」の内容によるものです。「ひので」はわが国が世界に誇る国産人工衛星で、太陽(特に黒点)観測を目的とし、2006年9月に打ち上げられ現在も稼働中で、時々刻々と観測データを地球に送り続けています。
番組の前編はこの太陽活動の観測結果による異変についての解説で、その異変とは、5/6の本ブログで紹介した内容と同様です。(黒点増減周期と太陽南極、北極の磁極反転の異変)
太陽黒点の増減を観測し始めた400年前のガリレオ・ガリレイの時代から、周期に異変のあった時期は過去2回あり、1810年頃と1680年頃で、この時は小氷期でロンドンのテムズ川が氷結したり、日本でも冷害による大飢饉があったとの記録が残っているようです。

(出所:英ウィキペディア テムズ川凍結画1814年)

(出所:英ウィキペディア テムズ川凍結画1683~1684年)
そこで、ここからは科学的推論になりますが、現在の黒点の増減の様子が過去2回の小氷期に似ており、従って近未来に小氷期が来るであろうと言うものです。又、寒冷化の原因は、太陽から来る熱・光エネルギーそのものが弱まるのではなく、磁力線が弱まることによって磁力線のバリヤーが弱まり、宇宙から地球に降り注ぐ宇宙線が強くなって、雲の核になる物質が増え、それによって雲が増え、そのために太陽エネルギー(熱・光)が遮られて寒冷化するという訳です。
後編になると、太陽の異変が地球や人類に及ぼす影響は何かと言うお話ですが、これらは未だ良く判っていないとの前提での推論となります。
ここで、常田教授のお話は太陽黒点の増減周期が11年から14年程度に延びたらどうなるかの100年単位の推論であり、長沼准教授のお話は氷河期のスパンが10万年、そうでない期間が1万年と言う周期の話であり、これを同じ太陽の異変と言う土俵上で論じるのはいささか無理がある様に感じました。BSフジの意図がやや空回りした感じです。
本来なら我が国が世界に誇る国産人工衛星「ひので」が今までぼやけていた太陽黒点の様子がはっきり見えて判る様になって来た(立花隆さんの表現を借りれば、「目の悪い人がメガネなしで見ていたものが、度がピタリ合ったメガネで見たものとの差・・」と言う)ことに話題が集中しても良さそうですが、話を広げすぎたために、ピントがずれてしまった感があります(私の個人的感想)。
長沼准教授は専門の「極限環境の生物学」だけでなく、宇宙にも詳しいと言われる方であり、もっと違う内容のお話を聞けたのではないかと思われます。略歴によれば、宇宙飛行士を目指して応募し、最終選考まで残ったとのこと。(その時選考されたのが野口聡一宇宙飛行士)
地球寒冷化と地球温暖化をどう捉えたら良いのか、と言う点については未だ判らないと言うのが今のところの結論の様ですが、小氷期も気候の激変(小刻みな急変)があったとの記録が残っていて、温暖化でも気候の激変が起こると言われています。寒冷化を温暖化でチャラにする(寒ければ暖めれば良い)と言うような単純な図式ではないように思いますが、今のところ答えは未だない様です。願わくば、寒気と暖気がぶつかり合う寒冷・温暖前線上の気候の激しさが我々の後々の世代で日常的にならないことを祈るばかりです。

(出所:ウィキペディア 前線の雲)
この番組で課題として出たことは、
①各分野の研究者が縦割りで行っているのを、横串を通して幅広く議論する必要がある。
②人類の文明は氷河期ではない時期に創り上げたものであり、氷河期が来た場合の耐性はないので、これを考える必要がある。
③国産人工衛星は打ち上げに金が掛かるが、世界に誇れる技術であり、継続的に打ち上げられる様に国民の応援が欲しい。
④地球温暖化の要因は「疑わしきは排除せず」、真実を明らかにする努力を続ける。
と言うようなことだと思います。
ここで、常田教授のお話は太陽黒点の増減周期が11年から14年程度に延びたらどうなるかの100年単位の推論であり、長沼准教授のお話は氷河期のスパンが10万年、そうでない期間が1万年と言う周期の話であり、これを同じ太陽の異変と言う土俵上で論じるのはいささか無理がある様に感じました。BSフジの意図がやや空回りした感じです。
本来なら我が国が世界に誇る国産人工衛星「ひので」が今までぼやけていた太陽黒点の様子がはっきり見えて判る様になって来た(立花隆さんの表現を借りれば、「目の悪い人がメガネなしで見ていたものが、度がピタリ合ったメガネで見たものとの差・・」と言う)ことに話題が集中しても良さそうですが、話を広げすぎたために、ピントがずれてしまった感があります(私の個人的感想)。
長沼准教授は専門の「極限環境の生物学」だけでなく、宇宙にも詳しいと言われる方であり、もっと違う内容のお話を聞けたのではないかと思われます。略歴によれば、宇宙飛行士を目指して応募し、最終選考まで残ったとのこと。(その時選考されたのが野口聡一宇宙飛行士)
地球寒冷化と地球温暖化をどう捉えたら良いのか、と言う点については未だ判らないと言うのが今のところの結論の様ですが、小氷期も気候の激変(小刻みな急変)があったとの記録が残っていて、温暖化でも気候の激変が起こると言われています。寒冷化を温暖化でチャラにする(寒ければ暖めれば良い)と言うような単純な図式ではないように思いますが、今のところ答えは未だない様です。願わくば、寒気と暖気がぶつかり合う寒冷・温暖前線上の気候の激しさが我々の後々の世代で日常的にならないことを祈るばかりです。

(出所:ウィキペディア 前線の雲)
この番組で課題として出たことは、
①各分野の研究者が縦割りで行っているのを、横串を通して幅広く議論する必要がある。
②人類の文明は氷河期ではない時期に創り上げたものであり、氷河期が来た場合の耐性はないので、これを考える必要がある。
③国産人工衛星は打ち上げに金が掛かるが、世界に誇れる技術であり、継続的に打ち上げられる様に国民の応援が欲しい。
④地球温暖化の要因は「疑わしきは排除せず」、真実を明らかにする努力を続ける。
と言うようなことだと思います。
Posted by 富士三合目 at 17:43│Comments(0)
│環境・地球温暖化





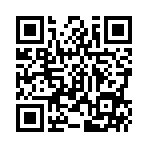



 MKビジネスサポート
MKビジネスサポート





