2012年05月06日
立花隆さんの気になる記事「太陽の謎」
月刊誌「文藝春秋」5月号(第九十巻第八号:2012年4月10日発売)の77~79頁にかけて、立花隆さんの<日本再生・十三(太陽の謎)>と言う評論が、「国立天文台の常田佐久教授の『新しい太陽像』」と題する講和を聞いて驚いた・・。」との書き出しで載っています。
この記事の内容は、日本の誇るJAXAの太陽観測衛星「ひので」(2006年9月打ち上げ現在稼働中)のデータを元にした世界各国の研究者の論文から太陽の謎の一部を解き明かしているものです。

(出所:JAXAホームページ 「太陽観測衛星ひので(SOLAR-B)」イメージ画)
この「ひので」には可視光・X線・極紫外線の3種類の望遠鏡を搭載しており、地球上のどの天文台にある望遠鏡よりも超高分解能・精密な画像が得られ(例えれば、目の悪い人がメガネなしで見るのと、度のピタリ合ったメガネを掛けて見る位の差)、更に凄いのは光学的には見ることの出来なかった磁力線・磁場の動きを目で見えるようにしたとのことで、この結果から、太陽黒点(実は太陽内部から出てくる磁力線の束の断面)の観測精度が飛躍的に上がり、今まで判らなかった「太陽の謎」の一部が解明されつつあるとのこと。その結果から大変気になる現象が明らかになってきました。
太陽黒点の観察は約400年前のガリレオ・ガリレイの時代から脈々と続けられており、従来、黒点は11年周期で増減しており、また、太陽の北極・南極の磁場(磁極)のプラス・マイナスがやはり11年周期で反転していたのが、北極11年周期、南極12.6年周期と反転のタイミングがずれ始めているとのこと。このままで行くと従来太陽の南のプラス極からから出て北のマイナス極に入る磁力線の二重極構造から、プラス極が北極にも南極にもあり、マイナス極が太陽の中緯度地帯に出来る四重極構造になるだろうと言われる。この結果、地球に及ぼす影響はどうなるか。

(出所:JAXAホームページ 従来の太陽二重極構造図)

(出所:JAXAホームページ 近未来の太陽四重極構造図)
この記事の内容は、日本の誇るJAXAの太陽観測衛星「ひので」(2006年9月打ち上げ現在稼働中)のデータを元にした世界各国の研究者の論文から太陽の謎の一部を解き明かしているものです。

(出所:JAXAホームページ 「太陽観測衛星ひので(SOLAR-B)」イメージ画)
この「ひので」には可視光・X線・極紫外線の3種類の望遠鏡を搭載しており、地球上のどの天文台にある望遠鏡よりも超高分解能・精密な画像が得られ(例えれば、目の悪い人がメガネなしで見るのと、度のピタリ合ったメガネを掛けて見る位の差)、更に凄いのは光学的には見ることの出来なかった磁力線・磁場の動きを目で見えるようにしたとのことで、この結果から、太陽黒点(実は太陽内部から出てくる磁力線の束の断面)の観測精度が飛躍的に上がり、今まで判らなかった「太陽の謎」の一部が解明されつつあるとのこと。その結果から大変気になる現象が明らかになってきました。
太陽黒点の観察は約400年前のガリレオ・ガリレイの時代から脈々と続けられており、従来、黒点は11年周期で増減しており、また、太陽の北極・南極の磁場(磁極)のプラス・マイナスがやはり11年周期で反転していたのが、北極11年周期、南極12.6年周期と反転のタイミングがずれ始めているとのこと。このままで行くと従来太陽の南のプラス極からから出て北のマイナス極に入る磁力線の二重極構造から、プラス極が北極にも南極にもあり、マイナス極が太陽の中緯度地帯に出来る四重極構造になるだろうと言われる。この結果、地球に及ぼす影響はどうなるか。

(出所:JAXAホームページ 従来の太陽二重極構造図)

(出所:JAXAホームページ 近未来の太陽四重極構造図)
太陽黒点の変化が地球環境に影響を与えるのは太陽エネルギー(熱・光)の変化ではなく、磁力線の影響と言われているが、その確証は得られていないとのこと。しかし、過去400年の歴史から推定出来るのは、1800年頃の小氷期と言われるダルトン極小期に似ており、更に周期が13年や14年になれば、400年前のマウンダー極小期と呼ばれる小氷期の再来(この時はロンドンのテムズ川が氷結した)になりかねないと言われる。
従来CO2排出増加による地球温暖化が叫ばれているが、この太陽の変化にも注目すべきとしており、この変化が地球に及ぼす影響は「小氷期時代は気候が不規則に急変した」と言われています。
巨大地震の周期は1000年に遡り、太陽黒点変化による気候変動の周期は400年に遡る時代になって来ました。人類の力の及ばない宇宙・地球規模の摂理と、人為的に起きているCO2排出増による地球温暖化(気候変動)とをどう折り合いをつけ、整理して人類を含む生物は生きて行けば良いのか、考えさせられてしまいます。
太陽観測衛星「ひので」による太陽の変化に関する国立天文台常田佐久教授の報告内容の詳細(2012年4月19日発表)は下記webサイトで見て下さい。
http://hinode.nao.ac.jp/news/120419PressRelease/PressRelease-20120419a-tsuneta.pdf
従来CO2排出増加による地球温暖化が叫ばれているが、この太陽の変化にも注目すべきとしており、この変化が地球に及ぼす影響は「小氷期時代は気候が不規則に急変した」と言われています。
巨大地震の周期は1000年に遡り、太陽黒点変化による気候変動の周期は400年に遡る時代になって来ました。人類の力の及ばない宇宙・地球規模の摂理と、人為的に起きているCO2排出増による地球温暖化(気候変動)とをどう折り合いをつけ、整理して人類を含む生物は生きて行けば良いのか、考えさせられてしまいます。
太陽観測衛星「ひので」による太陽の変化に関する国立天文台常田佐久教授の報告内容の詳細(2012年4月19日発表)は下記webサイトで見て下さい。
http://hinode.nao.ac.jp/news/120419PressRelease/PressRelease-20120419a-tsuneta.pdf
Posted by 富士三合目 at 02:02│Comments(0)
│環境・地球温暖化





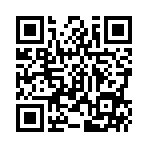



 MKビジネスサポート
MKビジネスサポート





