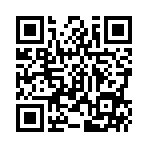2012年02月07日
遂に「SACLA(さくら)」来月稼動!
理化学研究所の最先端X線レーザー研究施設「SACLA(さくら)」が完成し、3月から本格稼動すると発表されました。この設備は日本企業500社の技術を結集したもので、その性能は欧米の同様の施設をしのぐと言われています。
X線レーザーはX線撮影の様に中身を透かし見ながら、原子の大きさまで観察できるため、「夢の光」と言われ、欧米でも同様の施設が建設されているとのこと。しかし、SACLAは欧米のものと比較しても格段に小型で且つ高性能です。全長は700mですが、2009年に完成した米国の施設は2,000m、2013年に稼動予定の欧州の施設は3,300mもあり、SACLAはそれと比較するとはるかに小型で、且つ細かい物を見る性能は米国のほぼ2倍、欧州より約3割高く、更に、建設費用もSACLAが約390億円に対し、米国は約470億円、欧州は約900億円以上となっています。
これを可能にしたのが、全長700mの「線形加速器」と言われるもので、日本の企業が技術を結集して開発したもので電子を短距離で光の速度まで高め、品質のそろったX線レーザーを作り出すことに成功したとのことです。
電子を加速する強力なマイクロ波発生装置は東芝が担当、加速部分のシステムは三菱重工が設計し、この装置に使われた銅は日立電線製で、純度を99.99%以上に高めている。光速の電子からX線レーザーを発生させる装置には、日立金属が開発した磁石が使用され、真空中でも性能が落ちないのが特徴で、装置内部に設置されている。真空では性能が出ず、装置の外に磁石を並べた欧米の装置よりも強い磁場が発生するため、性能が高まったとのこと。(2月7日付日経新聞朝刊)
大した「優れもの」といえましよう。

(出所:理化学研究所HPより 昨年6月X線レーザー発振に成功したときのポスター)

(出所:理化学研究所HPより SACLAの全景で、手前の直線部分が全長700mの線形加速器、円形部分はSPring-8)
続きを読む
X線レーザーはX線撮影の様に中身を透かし見ながら、原子の大きさまで観察できるため、「夢の光」と言われ、欧米でも同様の施設が建設されているとのこと。しかし、SACLAは欧米のものと比較しても格段に小型で且つ高性能です。全長は700mですが、2009年に完成した米国の施設は2,000m、2013年に稼動予定の欧州の施設は3,300mもあり、SACLAはそれと比較するとはるかに小型で、且つ細かい物を見る性能は米国のほぼ2倍、欧州より約3割高く、更に、建設費用もSACLAが約390億円に対し、米国は約470億円、欧州は約900億円以上となっています。
これを可能にしたのが、全長700mの「線形加速器」と言われるもので、日本の企業が技術を結集して開発したもので電子を短距離で光の速度まで高め、品質のそろったX線レーザーを作り出すことに成功したとのことです。
電子を加速する強力なマイクロ波発生装置は東芝が担当、加速部分のシステムは三菱重工が設計し、この装置に使われた銅は日立電線製で、純度を99.99%以上に高めている。光速の電子からX線レーザーを発生させる装置には、日立金属が開発した磁石が使用され、真空中でも性能が落ちないのが特徴で、装置内部に設置されている。真空では性能が出ず、装置の外に磁石を並べた欧米の装置よりも強い磁場が発生するため、性能が高まったとのこと。(2月7日付日経新聞朝刊)
大した「優れもの」といえましよう。

(出所:理化学研究所HPより 昨年6月X線レーザー発振に成功したときのポスター)

(出所:理化学研究所HPより SACLAの全景で、手前の直線部分が全長700mの線形加速器、円形部分はSPring-8)
続きを読む
2012年02月06日
宇宙から見たオーロラ展2012開催中
コニカミノルタホールディングスと宇宙航空研究開発機構(JAXA)共催で、「宇宙から見たオーロラ展2012」をコニカミノルタプラザ(東京・新宿区)にて1月20日(金)から2月19日(日)まで10:30~19:00(入場無料)で無休開催中です。今回はJAXAとNHKが共同開発した世界初の宇宙用超高感度ハイビジョンカメラシステムを国際宇宙ステーションに持ち込み、古川宇宙飛行士が昨年10月撮影し、NASAから映像が発表されたものが展示されているとのことです。
寒い冬の夜はなんとなくオーロラのイメージが頭に浮かんで来ます。東京に行く機会のある方はご覧になっては如何でしょうか。

(出所:JAXA「宇宙から見たオーロラ展2012」ポスター)

(出所:NASA映像 宇宙用超高感度ハイビジョンカメラを持つ国際宇宙ステーション内の古川宇宙飛行士)

(出所:NASA映像 YouTubeより)
続きを読む
寒い冬の夜はなんとなくオーロラのイメージが頭に浮かんで来ます。東京に行く機会のある方はご覧になっては如何でしょうか。

(出所:JAXA「宇宙から見たオーロラ展2012」ポスター)

(出所:NASA映像 宇宙用超高感度ハイビジョンカメラを持つ国際宇宙ステーション内の古川宇宙飛行士)

(出所:NASA映像 YouTubeより)
続きを読む
2012年02月04日
風景に溶け込む「春耕道しるべ」
富士市内にある「春耕道しるべ」は個人宅保存を除き、概ね全部(38基)個々に見てきたので、今回はウォーキングを楽しみながら、其々の「道しるべ」が周りの景色に溶け込んでたたずんでいる様子を紹介します。
今回は神戸地区の「歩く健康づくり一万歩、神戸みちしるべコース」を主体に歩いてみます。
出発点は吉原北中東南にある「春耕道しるべ第10号」からです。


(背景に愛鷹山と新東名高速道路が見える第10号)
次は新東名側道にたたづむ第11号です。


(新東名のトンネルが直ぐそばにあります。)
続いて新東名から200m程上った小高い場所に建つ第12号です。


(「東部建鉄㈱」さん前の分岐路茶畑角に第12号はあります。)
更に吉永第二小の方角に200m程上って行くと吉永第二小を背景に第32号があります。


(この辺りから富士山も駿河湾も良く見える茶畑が続きます。
ここで吉永第二小の周りを半周して反対側に出ます。

(この道を下って行くと鵜無ケ渕方面で県道76号線と合流します。右側青いフェンスは吉永第二小校庭、左側に昔春耕さんが歩いた古道があります)

(茶畑の脇を行く昔ながらの舗装してない道です。)
この先の県道76号線との合流点に第34号があります。(県道76号線は鵜無ケ淵で左に直角に曲がり200m程でこの合流点に来ます。)

(県道76号線側から見た分岐路、左が前記古道、右側は吉永第二小方面への新道で、分岐点に第34号があります。)

(第34号の表示塔が折れて倒れています。)
右側の新道を吉永第二小校庭方向に戻ると、校庭の西北角付近に第33号があります。


(背後に積んであるのは何でしょうか。第33号です。)
吉永第二小校庭脇を100m程進むと右に折れる脇道があり、その角に第31号があります。(吉永第二小の西南)

更に50m程坂道を上ると第30号が高圧送電線鉄塔の下の分岐点にあります。


(右側の道を行くと今宮方向になり、この辺りは富士山、愛鷹山、駿河湾が見える絶景ポイントです。)

(第30号から200m程上った分岐路に第38号があります。分岐点の左を見れば富士山です。)

(分岐点の右側を見れば愛鷹山です。この第38号は小さい石で出来た可愛い道しるべです。)
分岐点左側の道を200m程上って行くと第37号が茶畑の角にあります。ここは背景が駿河湾になります。

(分岐点に建つ第37号、左に行くと前記第38号の方角です。)
続きを読む
今回は神戸地区の「歩く健康づくり一万歩、神戸みちしるべコース」を主体に歩いてみます。
出発点は吉原北中東南にある「春耕道しるべ第10号」からです。
(背景に愛鷹山と新東名高速道路が見える第10号)
次は新東名側道にたたづむ第11号です。
(新東名のトンネルが直ぐそばにあります。)
続いて新東名から200m程上った小高い場所に建つ第12号です。
(「東部建鉄㈱」さん前の分岐路茶畑角に第12号はあります。)
更に吉永第二小の方角に200m程上って行くと吉永第二小を背景に第32号があります。
(この辺りから富士山も駿河湾も良く見える茶畑が続きます。
ここで吉永第二小の周りを半周して反対側に出ます。
(この道を下って行くと鵜無ケ渕方面で県道76号線と合流します。右側青いフェンスは吉永第二小校庭、左側に昔春耕さんが歩いた古道があります)
(茶畑の脇を行く昔ながらの舗装してない道です。)
この先の県道76号線との合流点に第34号があります。(県道76号線は鵜無ケ淵で左に直角に曲がり200m程でこの合流点に来ます。)
(県道76号線側から見た分岐路、左が前記古道、右側は吉永第二小方面への新道で、分岐点に第34号があります。)
(第34号の表示塔が折れて倒れています。)
右側の新道を吉永第二小校庭方向に戻ると、校庭の西北角付近に第33号があります。
(背後に積んであるのは何でしょうか。第33号です。)
吉永第二小校庭脇を100m程進むと右に折れる脇道があり、その角に第31号があります。(吉永第二小の西南)
更に50m程坂道を上ると第30号が高圧送電線鉄塔の下の分岐点にあります。
(右側の道を行くと今宮方向になり、この辺りは富士山、愛鷹山、駿河湾が見える絶景ポイントです。)
(第30号から200m程上った分岐路に第38号があります。分岐点の左を見れば富士山です。)
(分岐点の右側を見れば愛鷹山です。この第38号は小さい石で出来た可愛い道しるべです。)
分岐点左側の道を200m程上って行くと第37号が茶畑の角にあります。ここは背景が駿河湾になります。
(分岐点に建つ第37号、左に行くと前記第38号の方角です。)
続きを読む
2012年02月03日
広見公園の「春耕道しるべ」由来
広見公園に「春耕道しるべ」が4基あり、第2号、第26号、第28号、第40号であることは説明板に書いてあるので判りますが、どれが何番なのか?、元はどこにあったのか?等は記載されていないので判りませんでしたが、先日「東図書館」から借りてきた「吉永郷土研究会」発行の本「仁藤春耕道しるべ」に詳しく記載されており、漸く疑問が解けてすっきりしたので、紹介します。
広見公園の4基の「春耕道しるべ」が並んだ写真に番号を付けて見ました。

(広見公園内にある「春耕道しるべ」4基の写真と番号(本ブログ筆者が提供))

(広見公園の「春耕道しるべ」説明板(再掲) 第2号、第26号、第28号、第40号の記載があります)
<春耕道しるべ第2号>
・この道しるべが元あった場所は、根方街道から間門方面へ北に向かう辻にあり、石原材木店の西の角で、スーパー伊東菓子店の前にあったとのこと。この辻は現在の県道76号線(富士・富士宮・由比線)分岐点ではなく、もう一つ赤渕川寄りの辻になります。この辻を北進して行くと富士岡橋のたもとを経て間門から勢子辻・御殿場まで行く道になります。尚、富士岡橋のたもとには「春耕道しるべ第3号」があります。

(広見公園内にある「春耕道しるべ第2号」(再掲)(後列向かって左側)」
(表面上部:一番上に富士山線図 向かって左方向に指差し図 十里木道三り半)
(表面下部:まかど十三丁 がうど うないがふち三十丁 いまみや いしゐ一り六丁 そうげんさわ二十三丁 くわざき一り半 せこつじ二り二十五丁)
(右横:吉永村富士岡)
(左横:明治三十九年 駿東郡原里村 いんの五り半 をぎはら六り七丁)
(裏面:下花守 仁藤春耕 屋号)
<春耕道しるべ第26号>
・元あった場所は桑崎から勢子辻に通ずる旧道のそのまた旧道の林の中から発見されたとのこと。現在ある新道を上って行くと、産業廃棄物の最終処分場があり、その直ぐ近くに千束川に掛かる御所舟橋があります。それを渡ると直ぐ右に分岐して勢子辻方面に行く林の中の旧道があり、その辺りです。

(広見公園内にある「春耕道しるべ第26号」(後列向かって右側)(再掲))
(右:なかじまへ十四丁半 左:くわざきへ十三丁 明治三十九年)

(御所舟橋から千束川上流方向を見る)
<春耕道しるべ第28号>
・この道しるべの元の場所は、勢子辻町の南入口の南方500mほど下った旧道で、すでに廃道になった檜(ヒノキ)の林の中にあったとのこと。

(広見公園内にある「春耕道しるべ第28号」前列向かって右側(再掲))
(右:やまみち 左:十りぎみち三十三丁 せこつじ六丁)

(県道24号線の国道469号との合流点を案内する道路標識で、合流点まで300mとなっている)
この辺りの左側に旧道入口があるものと思われます。
<春耕道しるべ第40号>
・この道しるべの元の場所は吉永第二小学校のすぐ下の南にあったとのこと。富士見台方面から鵜無ケ渕方面に向かう道と県道76号線が合流する地点となります。

(広見公園内にある「春耕道しるべ第40号」前列むかって左側(再掲))
(右:やまみち)

(第12号のある場所から見た分岐点 右方向は県道76号線との合流方向、左方向は吉永第二小方向で第32号があります。
右側が本道、左側は脇道です。)
続きを読む
広見公園の4基の「春耕道しるべ」が並んだ写真に番号を付けて見ました。
(広見公園内にある「春耕道しるべ」4基の写真と番号(本ブログ筆者が提供))
(広見公園の「春耕道しるべ」説明板(再掲) 第2号、第26号、第28号、第40号の記載があります)
<春耕道しるべ第2号>
・この道しるべが元あった場所は、根方街道から間門方面へ北に向かう辻にあり、石原材木店の西の角で、スーパー伊東菓子店の前にあったとのこと。この辻は現在の県道76号線(富士・富士宮・由比線)分岐点ではなく、もう一つ赤渕川寄りの辻になります。この辻を北進して行くと富士岡橋のたもとを経て間門から勢子辻・御殿場まで行く道になります。尚、富士岡橋のたもとには「春耕道しるべ第3号」があります。
(広見公園内にある「春耕道しるべ第2号」(再掲)(後列向かって左側)」
(表面上部:一番上に富士山線図 向かって左方向に指差し図 十里木道三り半)
(表面下部:まかど十三丁 がうど うないがふち三十丁 いまみや いしゐ一り六丁 そうげんさわ二十三丁 くわざき一り半 せこつじ二り二十五丁)
(右横:吉永村富士岡)
(左横:明治三十九年 駿東郡原里村 いんの五り半 をぎはら六り七丁)
(裏面:下花守 仁藤春耕 屋号)
<春耕道しるべ第26号>
・元あった場所は桑崎から勢子辻に通ずる旧道のそのまた旧道の林の中から発見されたとのこと。現在ある新道を上って行くと、産業廃棄物の最終処分場があり、その直ぐ近くに千束川に掛かる御所舟橋があります。それを渡ると直ぐ右に分岐して勢子辻方面に行く林の中の旧道があり、その辺りです。
(広見公園内にある「春耕道しるべ第26号」(後列向かって右側)(再掲))
(右:なかじまへ十四丁半 左:くわざきへ十三丁 明治三十九年)
(御所舟橋から千束川上流方向を見る)
<春耕道しるべ第28号>
・この道しるべの元の場所は、勢子辻町の南入口の南方500mほど下った旧道で、すでに廃道になった檜(ヒノキ)の林の中にあったとのこと。
(広見公園内にある「春耕道しるべ第28号」前列向かって右側(再掲))
(右:やまみち 左:十りぎみち三十三丁 せこつじ六丁)
(県道24号線の国道469号との合流点を案内する道路標識で、合流点まで300mとなっている)
この辺りの左側に旧道入口があるものと思われます。
<春耕道しるべ第40号>
・この道しるべの元の場所は吉永第二小学校のすぐ下の南にあったとのこと。富士見台方面から鵜無ケ渕方面に向かう道と県道76号線が合流する地点となります。
(広見公園内にある「春耕道しるべ第40号」前列むかって左側(再掲))
(右:やまみち)
(第12号のある場所から見た分岐点 右方向は県道76号線との合流方向、左方向は吉永第二小方向で第32号があります。
右側が本道、左側は脇道です。)
続きを読む
2012年02月01日
図書館で借りました!「仁藤春耕道しるべ」の本
「仁藤春耕道しるべ」の本が出版されていることは知っていましたが、中央図書館では見付からなくて、吉永まちづくりセンター内の「東図書館」に行ったら3冊あり、貸し出し対象となっていたので、借りて来ました。吉永郷土研究会の執筆・発行で平成13年4月22日第1刷、平成15年8月25日第2刷となっていて、全305頁の立派な本です。。わくわくしながら読みつつあります。

(「仁藤春耕道しるべ」の本 吉永郷土研究会発行)
この本の中には個々の道しるべの由来が詳しく記載されていて、私があれこれ想像しながら歩いて探索した時に疑問に思った点(例えば、この分岐点には「道しるべ」があっても良いはずだが・・)について殆どの答えが記載されていて感激です。やはり、疑問に思った場所には実際はあったのが道路拡張時に移転したり、消失してしまったりしていることが判りました。特に桑崎から勢子辻までの長い道のりで「道しるべ」が一つも見付からなかったのですが、元は4基あって、其々の移転先もはっきり記載されていて安心しました。その内2基(No26,28)は広見公園、1基(No27)は吉永まちづくりセンター、1基(No35)は個人の自宅に保管されているとのことです。
この続きは次回以降にしたいと思います。
(「仁藤春耕道しるべ」の本 吉永郷土研究会発行)
この本の中には個々の道しるべの由来が詳しく記載されていて、私があれこれ想像しながら歩いて探索した時に疑問に思った点(例えば、この分岐点には「道しるべ」があっても良いはずだが・・)について殆どの答えが記載されていて感激です。やはり、疑問に思った場所には実際はあったのが道路拡張時に移転したり、消失してしまったりしていることが判りました。特に桑崎から勢子辻までの長い道のりで「道しるべ」が一つも見付からなかったのですが、元は4基あって、其々の移転先もはっきり記載されていて安心しました。その内2基(No26,28)は広見公園、1基(No27)は吉永まちづくりセンター、1基(No35)は個人の自宅に保管されているとのことです。
この続きは次回以降にしたいと思います。