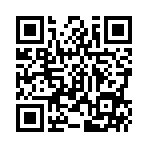2012年02月07日
遂に「SACLA(さくら)」来月稼動!
理化学研究所の最先端X線レーザー研究施設「SACLA(さくら)」が完成し、3月から本格稼動すると発表されました。この設備は日本企業500社の技術を結集したもので、その性能は欧米の同様の施設をしのぐと言われています。
X線レーザーはX線撮影の様に中身を透かし見ながら、原子の大きさまで観察できるため、「夢の光」と言われ、欧米でも同様の施設が建設されているとのこと。しかし、SACLAは欧米のものと比較しても格段に小型で且つ高性能です。全長は700mですが、2009年に完成した米国の施設は2,000m、2013年に稼動予定の欧州の施設は3,300mもあり、SACLAはそれと比較するとはるかに小型で、且つ細かい物を見る性能は米国のほぼ2倍、欧州より約3割高く、更に、建設費用もSACLAが約390億円に対し、米国は約470億円、欧州は約900億円以上となっています。
これを可能にしたのが、全長700mの「線形加速器」と言われるもので、日本の企業が技術を結集して開発したもので電子を短距離で光の速度まで高め、品質のそろったX線レーザーを作り出すことに成功したとのことです。
電子を加速する強力なマイクロ波発生装置は東芝が担当、加速部分のシステムは三菱重工が設計し、この装置に使われた銅は日立電線製で、純度を99.99%以上に高めている。光速の電子からX線レーザーを発生させる装置には、日立金属が開発した磁石が使用され、真空中でも性能が落ちないのが特徴で、装置内部に設置されている。真空では性能が出ず、装置の外に磁石を並べた欧米の装置よりも強い磁場が発生するため、性能が高まったとのこと。(2月7日付日経新聞朝刊)
大した「優れもの」といえましよう。

(出所:理化学研究所HPより 昨年6月X線レーザー発振に成功したときのポスター)

(出所:理化学研究所HPより SACLAの全景で、手前の直線部分が全長700mの線形加速器、円形部分はSPring-8)
続きを読む
X線レーザーはX線撮影の様に中身を透かし見ながら、原子の大きさまで観察できるため、「夢の光」と言われ、欧米でも同様の施設が建設されているとのこと。しかし、SACLAは欧米のものと比較しても格段に小型で且つ高性能です。全長は700mですが、2009年に完成した米国の施設は2,000m、2013年に稼動予定の欧州の施設は3,300mもあり、SACLAはそれと比較するとはるかに小型で、且つ細かい物を見る性能は米国のほぼ2倍、欧州より約3割高く、更に、建設費用もSACLAが約390億円に対し、米国は約470億円、欧州は約900億円以上となっています。
これを可能にしたのが、全長700mの「線形加速器」と言われるもので、日本の企業が技術を結集して開発したもので電子を短距離で光の速度まで高め、品質のそろったX線レーザーを作り出すことに成功したとのことです。
電子を加速する強力なマイクロ波発生装置は東芝が担当、加速部分のシステムは三菱重工が設計し、この装置に使われた銅は日立電線製で、純度を99.99%以上に高めている。光速の電子からX線レーザーを発生させる装置には、日立金属が開発した磁石が使用され、真空中でも性能が落ちないのが特徴で、装置内部に設置されている。真空では性能が出ず、装置の外に磁石を並べた欧米の装置よりも強い磁場が発生するため、性能が高まったとのこと。(2月7日付日経新聞朝刊)
大した「優れもの」といえましよう。

(出所:理化学研究所HPより 昨年6月X線レーザー発振に成功したときのポスター)

(出所:理化学研究所HPより SACLAの全景で、手前の直線部分が全長700mの線形加速器、円形部分はSPring-8)
続きを読む