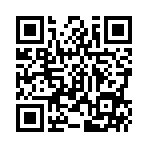2011年09月14日
「クラッシュ症候群」(ふじのくに防災士養成講座(3))
今回は「災害医療 東海地震に向けて」(講師:静岡県立総合病院救急診療部長 安田清先生)の講演内容から紹介します。この聞きなれない病名は阪神淡路大震災のときに明らかになった疾病名だそうです。地震で倒壊した家屋等の下敷きになっていた人を助け出し、外傷も殆どなく元気なので「やれやれ助かって良かった」と本人も周りの人達も喜んでいたのに、そのまま何もしなければ、突然死してしまうおそれのある疾病で、これを「クラッシュ症候群」と言い、阪神淡路大震災で最も患者が多かった(372人)のだそうです。
この病気の特長は「2時間以上物に挟まれていて、開放されたときに挟まれていた部分に麻痺がある場合」は「クラッシュ症候群」を疑ってその処置を速やかに行う必要があると言われています。

(静岡県ふじのくに防災士養成講座テキストP111より)
上から図1、図2,図3、図4、とすると
図1・・正常な血流
図2・・下肢の筋肉が圧迫されて静脈も動脈も血流が遮断されています。
図3・・この状態が長く続くと筋肉の細胞の膜が破れ、横紋筋融解症になります。しかし、ここ以外の体は普通に機能しており、意識も、呼吸も、血圧も、保たれています。
図4・・ここで圧迫が開放されると、筋肉にも再び血液が流れ始めます(再還流)。しかし、細胞の膜が壊れているために、細胞の中に水分が取り込まれてゆき、その結果体循環の水分が減り、脱水状態となって、急性腎不全を起こしてきます。また、壊れた筋肉細胞からカリウム、ミオグロビン等が静脈、体循環に流れ込んできて、カリウム濃度が高くなると瞬間的に心臓を止めてしまい、これが突然死の原因となるのだそうです。
続きを読む
この病気の特長は「2時間以上物に挟まれていて、開放されたときに挟まれていた部分に麻痺がある場合」は「クラッシュ症候群」を疑ってその処置を速やかに行う必要があると言われています。

(静岡県ふじのくに防災士養成講座テキストP111より)
上から図1、図2,図3、図4、とすると
図1・・正常な血流
図2・・下肢の筋肉が圧迫されて静脈も動脈も血流が遮断されています。
図3・・この状態が長く続くと筋肉の細胞の膜が破れ、横紋筋融解症になります。しかし、ここ以外の体は普通に機能しており、意識も、呼吸も、血圧も、保たれています。
図4・・ここで圧迫が開放されると、筋肉にも再び血液が流れ始めます(再還流)。しかし、細胞の膜が壊れているために、細胞の中に水分が取り込まれてゆき、その結果体循環の水分が減り、脱水状態となって、急性腎不全を起こしてきます。また、壊れた筋肉細胞からカリウム、ミオグロビン等が静脈、体循環に流れ込んできて、カリウム濃度が高くなると瞬間的に心臓を止めてしまい、これが突然死の原因となるのだそうです。
続きを読む