2011年09月08日
東海・東南海・南海地震(ふじのくに防災士養成講座(2))
前回の続きで、(財)地震予知総合研究振興会地震調査研究センター所長 阿部勝征東大名誉教授の講演のポイントを紹介します。阿部氏は東海地震判定会会長、中央防災会議委員、政府地震調査委員会委員長、日本災害情報学会会長も兼務されています。
東海・東南海・南海三連動地震については、プレート型地震であり、プレートの境界(駿河トラフ、南海トラフ)のどこかで引き金となって三連動する巨大地震は過去何回か起きている。1605年の慶長地震(M:7.9)、1707年宝永地震(M:8.6)、
1854年安政東海・東南海地震(M:8.4)、があり、1944年東南海地震(M:7.9)、1946年南海地震(M:8.0)はそれぞれ単独で起きたが、東海だけは空白域が156年あるため、いつ起きても不思議ではなく、今後30年間で発生確率87%となっているわけである。

(過去400年間の東海・東南海・南海地震の発生状況)
東海・東南海・南海三連動地震については、プレート型地震であり、プレートの境界(駿河トラフ、南海トラフ)のどこかで引き金となって三連動する巨大地震は過去何回か起きている。1605年の慶長地震(M:7.9)、1707年宝永地震(M:8.6)、
1854年安政東海・東南海地震(M:8.4)、があり、1944年東南海地震(M:7.9)、1946年南海地震(M:8.0)はそれぞれ単独で起きたが、東海だけは空白域が156年あるため、いつ起きても不思議ではなく、今後30年間で発生確率87%となっているわけである。

(過去400年間の東海・東南海・南海地震の発生状況)
次に、地震予知は可能か?については、「予知」とは「いつ、どこで、どの程度の地震」が起きるか知りたいわけであるが、「いつ」を予知するのが最も難しい。あとで考えれば「あれが地震の前兆だったか」、と言えるものはあるがこれはあくまで「あと予知」と言うもので、やりたいのは「まえ予知」である。しかし、現状では困難なのが実情である。尚、東海地震に関しては、震源が陸上の場合には観測網が張り巡らしてあるので、前兆をつかめる可能性はあるが、未だ一度もつかんだことがないので何とも言いがたい。震源が海域であれば観測網がないので、まず不可能といわざるを得ない。
地震の人的・経済的被害想定では、「東海」では死者9,400人、経済26~37兆円、「東海+東南海」で死者13,400人、経済38~57兆円、「東海+東南海+南海」で死者24,800人、経済53~81兆円であるが、実際にはもっと大きくなることが予想される。この地域は海岸沿いに人口密集、産業集中していて、古い木造家屋が多いからである。
以上のことから、「地震予知は困難」と言うことに留意し、今後10年間で想定被害の半分に減災することを戦略とするのが望ましい。そのためには
①物的被害量軽減のためには建物の耐震化
②人的被害軽減のためには津波避難対策
③中枢機能の継続性確保のためには事業継続計画(BCP)の策定
を減災の柱とすべきと考える。
以上ですが、ポイントのずれている点があればご容赦下さい。
地震の人的・経済的被害想定では、「東海」では死者9,400人、経済26~37兆円、「東海+東南海」で死者13,400人、経済38~57兆円、「東海+東南海+南海」で死者24,800人、経済53~81兆円であるが、実際にはもっと大きくなることが予想される。この地域は海岸沿いに人口密集、産業集中していて、古い木造家屋が多いからである。
以上のことから、「地震予知は困難」と言うことに留意し、今後10年間で想定被害の半分に減災することを戦略とするのが望ましい。そのためには
①物的被害量軽減のためには建物の耐震化
②人的被害軽減のためには津波避難対策
③中枢機能の継続性確保のためには事業継続計画(BCP)の策定
を減災の柱とすべきと考える。
以上ですが、ポイントのずれている点があればご容赦下さい。
Posted by 富士三合目 at 00:48│Comments(0)
│津波・地震避難訓練





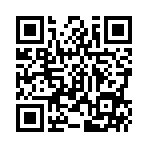



 MKビジネスサポート
MKビジネスサポート




