2011年10月30日
大震災と「鯰(なまず)絵」(その2)
富士市立博物館で見た「鯰(なまず)絵」が珍しかったので、ネットで調べて見ました。いろいろな鯰絵があることが判ったので、その一部を紹介します。
鯰(なまず)絵は、安政2年(1855年)10月の安政大地震の後、いろいろな図柄のものが流行ったようですが、一番典型的な図柄は鹿島大明神が要石(かなめいし)で鯰を押さえつけて地震を鎮めており、これを庶民は護符(お守り)として買って、家の中に貼り付けておいたのだそうです。

(要石で押さえ付けられた大鯰:社会事業大学図書館)
庶民が総出で大鯰を押さえ込んでいる絵もあり、これは庶民が「世直し」を望んでいる表れの様です。これも梵字(ぼんじ)で書かれた護符となっています。

(鯰退治の図:社会事業大学図書館)
鯰(なまず)絵は、安政2年(1855年)10月の安政大地震の後、いろいろな図柄のものが流行ったようですが、一番典型的な図柄は鹿島大明神が要石(かなめいし)で鯰を押さえつけて地震を鎮めており、これを庶民は護符(お守り)として買って、家の中に貼り付けておいたのだそうです。

(要石で押さえ付けられた大鯰:社会事業大学図書館)
庶民が総出で大鯰を押さえ込んでいる絵もあり、これは庶民が「世直し」を望んでいる表れの様です。これも梵字(ぼんじ)で書かれた護符となっています。

(鯰退治の図:社会事業大学図書館)
もう一枚珍しいのは、安政大地震が1855年10月に起きており、丁度10月は「神無月」で、神々が出雲大社に出かけて留守のため「神無月」と言われている訳で、その間「恵比寿天が留守神」をしていたところに地震を起こす不始末をしてしまい、鹿島大明神の前で、鯰たちを従え、申し開きをしている図です。

(恵比寿天申し開きの図:社会事業大学図書館)
これらの絵を見ると、当時の世相や、人々の想像力の豊かさが感じられます。

(恵比寿天申し開きの図:社会事業大学図書館)
これらの絵を見ると、当時の世相や、人々の想像力の豊かさが感じられます。
Posted by 富士三合目 at 03:01│Comments(0)
│津波・地震避難訓練





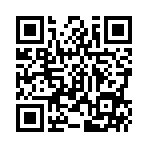



 MKビジネスサポート
MKビジネスサポート




