2012年04月16日
御殿場市の「春耕道しるべ」(2)
前回の続きで、御殿場市の「春耕道しるべ」探索記です。
滝ケ原の「長井酒店前」No20と「佐藤洋服店横」No21の続きは同じく滝ケ原地区の「瀧ケ原不動尊」にあるNo23、24、25の3基です。元は別の場所にあったものを、ゴルフ場開発や、道路拡張工事等で移動せざるを得なくなり、春耕さんゆかりの瀧ケ原不動尊に移設したとのことです。

(春耕さんゆかりの「瀧ケ原不動尊」石碑)


(灯篭が「春耕燈」となっています)

(瀧ケ原不動尊の由来を彫った顕彰碑 春耕さんを顕彰しています)

(3基並んで建っている 字は薄くて読取りにくい)
左から一番大きいNo25、No23、No24となっています。

No25・・富士山頂へ三里三十一丁半 一里松へ二十一丁半 馬返へ一里十四丁 昼食場へ一里二十七丁半 太郎坊へ一里三十二丁 二合へ二里十二丁半 二合二勺へ二里二十二丁 二合五勺へ二里二十六丁 三合へ二里三十三丁半 四合へ三里二丁半 五合へ三里九丁 六合へ三里十四丁半 七合へ三里十八丁 七合五勺へ三里二十一丁 八合へ三里二十八丁半 九合へ三里三十丁
No25は「富士山里程の道しるべ」と言われている様です。又、裏面には春耕さんが「道しるべと瀧ケ原不動尊」を建立するに至った趣旨を刻んでいます。

No23・・右だんごう 左十りぎ

No24・・左指差し←すばしり
瀧ケ原不動尊のお祭りは毎年4月末に地元の人達と、仁藤家の春耕さんゆかりの人達で行われているとのことなので、もう直ぐ行われることでしょう。
滝ケ原の「長井酒店前」No20と「佐藤洋服店横」No21の続きは同じく滝ケ原地区の「瀧ケ原不動尊」にあるNo23、24、25の3基です。元は別の場所にあったものを、ゴルフ場開発や、道路拡張工事等で移動せざるを得なくなり、春耕さんゆかりの瀧ケ原不動尊に移設したとのことです。
(春耕さんゆかりの「瀧ケ原不動尊」石碑)
(灯篭が「春耕燈」となっています)
(瀧ケ原不動尊の由来を彫った顕彰碑 春耕さんを顕彰しています)
(3基並んで建っている 字は薄くて読取りにくい)
左から一番大きいNo25、No23、No24となっています。
No25・・富士山頂へ三里三十一丁半 一里松へ二十一丁半 馬返へ一里十四丁 昼食場へ一里二十七丁半 太郎坊へ一里三十二丁 二合へ二里十二丁半 二合二勺へ二里二十二丁 二合五勺へ二里二十六丁 三合へ二里三十三丁半 四合へ三里二丁半 五合へ三里九丁 六合へ三里十四丁半 七合へ三里十八丁 七合五勺へ三里二十一丁 八合へ三里二十八丁半 九合へ三里三十丁
No25は「富士山里程の道しるべ」と言われている様です。又、裏面には春耕さんが「道しるべと瀧ケ原不動尊」を建立するに至った趣旨を刻んでいます。
No23・・右だんごう 左十りぎ
No24・・左指差し←すばしり
瀧ケ原不動尊のお祭りは毎年4月末に地元の人達と、仁藤家の春耕さんゆかりの人達で行われているとのことなので、もう直ぐ行われることでしょう。
瀧ケ原不動尊の次は「川柳(かわやなぎ)浅間神社」付近のNo54、53、19の探索です。瀧ケ原不動尊から1km位印野の方角に戻ります。


(川柳浅間神社には樹齢500年以上の「扶桑(夫婦)杉」があります)

(扶桑杉の説明板)
川柳浅間神社の前に遠慮がちに小さな道しるべNo54号が建っていました。地元の高校生が扶桑杉の見学に来ていました。



(春耕道しるべNo54号)
No54・・右すばしり
この近くにNo53があるはずでしたが見当たらず、No19を探索しました。
県道155号線(滝ケ原富士岡線)との合流点手前に他の石碑と一緒に建てられていました。


(向かって一番右側がNo19となります。)

No19・・右指差し→すばしりみち一り廿六丁
これで御殿場市にあると言われている13基の内、No19、20、21、23、24、25、49、50、51、52、54、の計11基が確認で出来ました。残るは、裾野市須山のNo46、御殿場市水土野三味線坂のNo22、川柳のNo53の3基です。いずれ再挑戦して見ようと思います。
(川柳浅間神社には樹齢500年以上の「扶桑(夫婦)杉」があります)
(扶桑杉の説明板)
川柳浅間神社の前に遠慮がちに小さな道しるべNo54号が建っていました。地元の高校生が扶桑杉の見学に来ていました。
(春耕道しるべNo54号)
No54・・右すばしり
この近くにNo53があるはずでしたが見当たらず、No19を探索しました。
県道155号線(滝ケ原富士岡線)との合流点手前に他の石碑と一緒に建てられていました。
(向かって一番右側がNo19となります。)
No19・・右指差し→すばしりみち一り廿六丁
これで御殿場市にあると言われている13基の内、No19、20、21、23、24、25、49、50、51、52、54、の計11基が確認で出来ました。残るは、裾野市須山のNo46、御殿場市水土野三味線坂のNo22、川柳のNo53の3基です。いずれ再挑戦して見ようと思います。
Posted by 富士三合目 at 21:17│Comments(0)
│春耕道しるべ





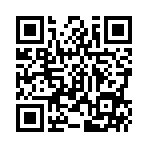



 MKビジネスサポート
MKビジネスサポート