2012年05月11日
NHKクローズアップ現代の「海洋発電」
5月10日(木)19:30からNHKクローズアップ現代で「海から電気を造り出す!その可能性と課題は?」と言う番組が放送されました。わが国において、「海洋発電」は話題には上っても殆ど注目されずに過ぎて来ましたが、イギリスにおいては国家プロジェクトとして開発を進めているようです。
「海洋発電」にはいろいろあって、以前本ブログでも紹介した「海水温度差発電」、「塩分濃度差(浸透圧)発電」の他に「潮流(力)発電」や「波力発電」等がありますが、今日の番組では主として「潮力発電」と「波力発電」についてでした。
「潮力発電」は潮の流れによるエネルギーをプロペラの回転によって電力に変換するもので、潮流の速い場所で且つ、発電機(スクリュー)を設置するためのゲート状の建造物が建てられる比較的海底が浅い立地条件が必要となり、場所は限定されるように感じました。海上にゲートを建てるので、船舶の往来するような海峡には潮の流れがあっても設置はかなり制約されそうです。
発電用プロペラ(スクリュー)の開発競争に川崎重工業が参戦している様子が番組中で放映されていました。

(出所:NHKオンライン イギリスの潮力発電施設)
一方の「波力発電」は波の上下運動を空気圧やピストン運動(→回転運動)として捉え、電気に変換する方法で、一見ノンビリした感じがしますが、イギリスでは「海ヘビ」と名付けられた細長い浮遊物の連結部で伸縮運動をピストン運動に変換していました。これなどは、海上にただ浮かべて置くだけなので、場所さえあれば、可能性はありそうと感じました。しかし、日本では漁業権との兼ね合いや、規制で、設置までの手続きに大変な労力と時間が掛かるようです。又、発電効率は余り高くなさそう(それでも太陽光発電よりも数倍高いらしい)なので、発電コストがどうなるかが課題のようです。それらを実証するためには、実証プラントを設置してテストする必要があるわけですが、その設置場所の許可を得るのに苦労している様子でした。こちらの方はベンチャー企業が開発しているケースが多く、資金調達も大変とのことです。
「海洋発電」にはいろいろあって、以前本ブログでも紹介した「海水温度差発電」、「塩分濃度差(浸透圧)発電」の他に「潮流(力)発電」や「波力発電」等がありますが、今日の番組では主として「潮力発電」と「波力発電」についてでした。
「潮力発電」は潮の流れによるエネルギーをプロペラの回転によって電力に変換するもので、潮流の速い場所で且つ、発電機(スクリュー)を設置するためのゲート状の建造物が建てられる比較的海底が浅い立地条件が必要となり、場所は限定されるように感じました。海上にゲートを建てるので、船舶の往来するような海峡には潮の流れがあっても設置はかなり制約されそうです。
発電用プロペラ(スクリュー)の開発競争に川崎重工業が参戦している様子が番組中で放映されていました。

(出所:NHKオンライン イギリスの潮力発電施設)
一方の「波力発電」は波の上下運動を空気圧やピストン運動(→回転運動)として捉え、電気に変換する方法で、一見ノンビリした感じがしますが、イギリスでは「海ヘビ」と名付けられた細長い浮遊物の連結部で伸縮運動をピストン運動に変換していました。これなどは、海上にただ浮かべて置くだけなので、場所さえあれば、可能性はありそうと感じました。しかし、日本では漁業権との兼ね合いや、規制で、設置までの手続きに大変な労力と時間が掛かるようです。又、発電効率は余り高くなさそう(それでも太陽光発電よりも数倍高いらしい)なので、発電コストがどうなるかが課題のようです。それらを実証するためには、実証プラントを設置してテストする必要があるわけですが、その設置場所の許可を得るのに苦労している様子でした。こちらの方はベンチャー企業が開発しているケースが多く、資金調達も大変とのことです。
潮力発電や波力発電は過去日本でも1980年代にかなり盛んに実証試験は行われたようですが、ほとんどが、実験終了という形で実用化には至らず中断(終了)されているようです。(一部現在でも実験している施設もある様ですが・・) その後日本は国を挙げて原子力発電に注力してきた結果ですが、原発の存続が議論されている今、海洋国の日本としては、海洋エネルギーを生かした「海洋発電」に再度目を向けても良いのではかいかと思います。
波力発電の場合、もし、事業として成り立つ程度のものであれば、素人の思い付きですが、漁協が主体となって、「魚の養殖」と同じように、「電気の養殖?」をして見てはどうでしょうか。えさもいらず、赤潮や病気の心配もなく、ただ浮かべておけばそれなりの電気をコンスタントに生み出してくれます。この電力を売るなり、漁業関係の施設等で利用したらどうでしょうか。
日本で本格的に試験運転した波力発電施設としては、三重県でのマイティホエールがあります(1998年9月~2002年3月)。これは、海洋科学研究センター(現(独)科学技術振興機構)が行ったもので、波力発電と太陽光発電と組み合わせて、お互いの欠点を補い合っていたとのことです。即ち、波力発電は天気の良いときは波が静かで発電が弱く、一方太陽光発電は天気の良いときは発電能力が高く、天気の悪いときはその逆で丁度補完し合う状態になります。これなどは良いアイディアだと感心しました。これに蓄電設備が加わればもっと良くなったでしょう。10年前に実験が終了してしまっているとはまことに残念です。



(出所:海洋科学研究センター報告 マイティホエール)
波力発電の場合、もし、事業として成り立つ程度のものであれば、素人の思い付きですが、漁協が主体となって、「魚の養殖」と同じように、「電気の養殖?」をして見てはどうでしょうか。えさもいらず、赤潮や病気の心配もなく、ただ浮かべておけばそれなりの電気をコンスタントに生み出してくれます。この電力を売るなり、漁業関係の施設等で利用したらどうでしょうか。
日本で本格的に試験運転した波力発電施設としては、三重県でのマイティホエールがあります(1998年9月~2002年3月)。これは、海洋科学研究センター(現(独)科学技術振興機構)が行ったもので、波力発電と太陽光発電と組み合わせて、お互いの欠点を補い合っていたとのことです。即ち、波力発電は天気の良いときは波が静かで発電が弱く、一方太陽光発電は天気の良いときは発電能力が高く、天気の悪いときはその逆で丁度補完し合う状態になります。これなどは良いアイディアだと感心しました。これに蓄電設備が加わればもっと良くなったでしょう。10年前に実験が終了してしまっているとはまことに残念です。



(出所:海洋科学研究センター報告 マイティホエール)
Posted by 富士三合目 at 00:53│Comments(0)
│新エネルギー





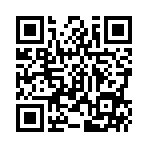



 MKビジネスサポート
MKビジネスサポート




