2011年08月16日
「コマツ」に見る日本国籍のグローバル企業
日経新聞に「新しい日本へ」(復興の道筋を聞く)と言うシリーズ記事が出ており、第一回目はコマツ会長の坂根正弘氏へのインタビュー内容です。
「コマツ」はグローバル企業でありながら、国内の協力企業も大事にし、東日本大震災でもそのサプライチェーンを活用して、驚異的な速さで復旧を遂げ、「腹の据わった日本国籍グローバル企業」と言われています。どの様な考え方で事業を営んでいるのか、少し長い記事ですが見てみましょう。
大きな見出しは(過当競争脱却し海外へ)です。

「コマツ」はグローバル企業でありながら、国内の協力企業も大事にし、東日本大震災でもそのサプライチェーンを活用して、驚異的な速さで復旧を遂げ、「腹の据わった日本国籍グローバル企業」と言われています。どの様な考え方で事業を営んでいるのか、少し長い記事ですが見てみましょう。
大きな見出しは(過当競争脱却し海外へ)です。

(Q1)・・円高に電力不足と、製造業に強い逆風が吹きつけている。
(A1)・・「コマツ」は建設機械を国内外で半分ずつ生産している。昨年度の営業利益は2200億円で、内1300億円は海外生産・販売で稼いだ。輸出の儲けは800億円、国内で造り、国内で売って得た利益は100億円にすぎない。なぜ日本では儲からないのか、いろいろ課題はあるものの、これは原発事故による電力不足以前からの課題であり、民間にできることは民間の手で解決するしかない。
(国内は消耗戦)
(Q2)・・根っこにある日本固有の課題は
(A2)・・「成長しないデフレ国家」であること。超低金利なのに物価下落で実質金利が高まり、円高になる最悪の展開。多少インフレになれば円高も解消される可能性がある。一刻も早くデフレを生む構造問題を解決すべき。「縮じむ国内市場にプレーヤーがいっぱいいて消耗戦をやっている。世界の製造業に欠かせない部品・素材企業が国内に多いことが震災で分かった。ただ過当競争だから、顧客に言われれば何でも引き受ける。こうした体質がいろんな業界で低収益を生んでいる。
(Q3)・・コマツは円高下でも輸出で稼いでいる
(A3)・・1980年代後半、当社は米国の2位メーカーを買い、ドイツやイタリアなどでも同業を買収した。業界再編を自ら主導したために日本を除けば過当競争がなくなり、それぞれの市場で稼げるようになった。「技術を磨き輸出競争力を高めるのは当然。加えて円高で苦しくとも値下げ競争には加わらず、率先して値上げしてきた。当社は中国を含むアジアの建機トップ。業界で強い立場だからこそ過当競争と無縁でいられる。そうでなければ日本で生産していられない。」
(Q4)・・日本でも大型再編の機運が高まってきた。成功させるには。
(A4)・・「雇用は大事」としながら、「一度始めた事業をやめる訳にはいかない」とも言う。長年やってきた事業をやめる決断をしない会社同士が一緒になっても成果が出ず、結局は雇用を失う。当社は事業をかなり整理し、子会社も減らした。犠牲にすべきところを犠牲にしない限り国際競争力は手にできない。これまでの日本人の特性も変わらざるを得ない。
(産業集積は強み)
(Q5)・・日本企業が生かすべき強みは何か。
(A5)・・あらゆる部品・素材を国内で調達できる産業集積がある。こんな国は世界にない。日本には大手と中小で賃金の二重構造がある。格差を縮める余力のない企業は中小の力を引き出せず、競争力が無くなる。協力企業は一心同体。(開発や資金調達などの)コストの一部を負担し、協力企業の賃上げを間接支援するという工夫が必要。
(Q6)・・協力企業の海外進出を後押ししている
(A6)・・思い切って海外に出た企業は当社以外との取引が拡大する、国内工場向けの注文が増え、日本に残った企業と比べて競争力を高めた事例がある。一見すれば空洞化のようでも、アジアの成長を取り込めれば果実は必ず日本に帰ってくる。
(Q7)・・株安・円高を受け、産業界には政府の支援を求める声もある
(A7)・・「環太平洋経済連携協定(TPP)」を巡る農業保護の議論もそうだが、守りに投じたカネは絶対に生きたものにはならない。じり貧になるだけだ。私が入社した年に米キャタピラーが日本に本格進出し、コマツはもうダメだと言われた。当時の社長は「攻撃は最大の防御」と説き、われわれは必死になって仕事した。今ほど製造業に攻めが求められている時はなく、攻めるなら海外だ。これだけの円高なのだから、借金してでも海外の会社を買うくらいの戦略に打ってでるべきだ。
以上で記事は終わりです。示唆に富むと言うか、考えさせられる記事です。
(A1)・・「コマツ」は建設機械を国内外で半分ずつ生産している。昨年度の営業利益は2200億円で、内1300億円は海外生産・販売で稼いだ。輸出の儲けは800億円、国内で造り、国内で売って得た利益は100億円にすぎない。なぜ日本では儲からないのか、いろいろ課題はあるものの、これは原発事故による電力不足以前からの課題であり、民間にできることは民間の手で解決するしかない。
(国内は消耗戦)
(Q2)・・根っこにある日本固有の課題は
(A2)・・「成長しないデフレ国家」であること。超低金利なのに物価下落で実質金利が高まり、円高になる最悪の展開。多少インフレになれば円高も解消される可能性がある。一刻も早くデフレを生む構造問題を解決すべき。「縮じむ国内市場にプレーヤーがいっぱいいて消耗戦をやっている。世界の製造業に欠かせない部品・素材企業が国内に多いことが震災で分かった。ただ過当競争だから、顧客に言われれば何でも引き受ける。こうした体質がいろんな業界で低収益を生んでいる。
(Q3)・・コマツは円高下でも輸出で稼いでいる
(A3)・・1980年代後半、当社は米国の2位メーカーを買い、ドイツやイタリアなどでも同業を買収した。業界再編を自ら主導したために日本を除けば過当競争がなくなり、それぞれの市場で稼げるようになった。「技術を磨き輸出競争力を高めるのは当然。加えて円高で苦しくとも値下げ競争には加わらず、率先して値上げしてきた。当社は中国を含むアジアの建機トップ。業界で強い立場だからこそ過当競争と無縁でいられる。そうでなければ日本で生産していられない。」
(Q4)・・日本でも大型再編の機運が高まってきた。成功させるには。
(A4)・・「雇用は大事」としながら、「一度始めた事業をやめる訳にはいかない」とも言う。長年やってきた事業をやめる決断をしない会社同士が一緒になっても成果が出ず、結局は雇用を失う。当社は事業をかなり整理し、子会社も減らした。犠牲にすべきところを犠牲にしない限り国際競争力は手にできない。これまでの日本人の特性も変わらざるを得ない。
(産業集積は強み)
(Q5)・・日本企業が生かすべき強みは何か。
(A5)・・あらゆる部品・素材を国内で調達できる産業集積がある。こんな国は世界にない。日本には大手と中小で賃金の二重構造がある。格差を縮める余力のない企業は中小の力を引き出せず、競争力が無くなる。協力企業は一心同体。(開発や資金調達などの)コストの一部を負担し、協力企業の賃上げを間接支援するという工夫が必要。
(Q6)・・協力企業の海外進出を後押ししている
(A6)・・思い切って海外に出た企業は当社以外との取引が拡大する、国内工場向けの注文が増え、日本に残った企業と比べて競争力を高めた事例がある。一見すれば空洞化のようでも、アジアの成長を取り込めれば果実は必ず日本に帰ってくる。
(Q7)・・株安・円高を受け、産業界には政府の支援を求める声もある
(A7)・・「環太平洋経済連携協定(TPP)」を巡る農業保護の議論もそうだが、守りに投じたカネは絶対に生きたものにはならない。じり貧になるだけだ。私が入社した年に米キャタピラーが日本に本格進出し、コマツはもうダメだと言われた。当時の社長は「攻撃は最大の防御」と説き、われわれは必死になって仕事した。今ほど製造業に攻めが求められている時はなく、攻めるなら海外だ。これだけの円高なのだから、借金してでも海外の会社を買うくらいの戦略に打ってでるべきだ。
以上で記事は終わりです。示唆に富むと言うか、考えさせられる記事です。
Posted by 富士三合目 at 01:14│Comments(0)
│ビジネス





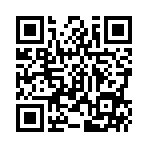



 MKビジネスサポート
MKビジネスサポート





