2011年08月10日
地域力強化の鍵「(地元)国立大学への期待」
8月8日の日経新聞朝刊「教育」欄に国立大学協会が国立大学法人化8年目にしてまとめた「国立大学の機能強化ーー国民への約束」の内容について発表されました。これも長文記事のため、全部を紹介するのは困難ですが、私の理解の範囲で要約して紹介します。
1)日本を支える根幹
①日本は東日本大震災からの復興・再生をはじめ厳しい困難な状況に直面している。こうした時代にこそ、全国86の国立大学が、それぞれの機能を最大限に発揮し、教育研究における競争力を徹底的に強化することで、明日の日本を支える根幹の役割を果たしていくことが必要である。
②国立大学法人の役割は、「大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、わが国の高等教育及び、学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図る」(国立大学法人法第1条)ことである。この報告書の副題を「国民への約束」としたのは、この役割への強い自覚の表明である。
③そして、この「約束」は、個々の国立大学が個性・特色を生かした取組みにまい進するとともに、国立大学全体が「有機的な連携共同システム」として総力を結集することにより果たされるものである。報告書で訴えたい眼目はここにある。
1)日本を支える根幹
①日本は東日本大震災からの復興・再生をはじめ厳しい困難な状況に直面している。こうした時代にこそ、全国86の国立大学が、それぞれの機能を最大限に発揮し、教育研究における競争力を徹底的に強化することで、明日の日本を支える根幹の役割を果たしていくことが必要である。
②国立大学法人の役割は、「大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、わが国の高等教育及び、学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図る」(国立大学法人法第1条)ことである。この報告書の副題を「国民への約束」としたのは、この役割への強い自覚の表明である。
③そして、この「約束」は、個々の国立大学が個性・特色を生かした取組みにまい進するとともに、国立大学全体が「有機的な連携共同システム」として総力を結集することにより果たされるものである。報告書で訴えたい眼目はここにある。
2)国立大学機能強化の証明(個性明確化、競争力を磨く)
①決め手は競争力である。この競争はいろいろなフェーズ、様々な切磋琢磨する対象がある。
②これらの機能強化の実現は、各大学における個性の明確化、ミッションの明示をはじめ、不断の改革の実行や質保証システムの確立、情報開示や、説明責任などを求めている。何よりもまず個々の大学の責任ある努力が重要である。
3)資源を効率的に
①大きな変化の中で、限られた資源の下で、一つの大学で対応するより連携することが、より効率的で生産的な場合もある。実際、地域で、あるいは地域を超えて、教育・研究組織の共同設置や設備等の共同利用、事務処理等の共同化などが着実に進んでいる。
②連携の相手は国立大学に限る必要はない。自らの個性と競争力を確保し、社会に貢献するために、単独で活動するのか、それとも他大学と連携するのか、各大学がしっかり考えるということである。
③国民への約束を果たしてゆく上で、国立大学への運営費交付金の削減や、人件費削減の流れは、まことに不合理なものである。国際的に見て、日本の高等教育に対する公的投資は著しく低い。「ヒト」こそが大学の競争力の源であることを強調したい。
4)2015年度中に実現
①十分な投資で国立大学の機能を強化することが、地域の力を強化し、国の力を強化し、何より大震災からの復興に向けて研究開発と人材育成を強化してゆくことに繋がる。
②このことが、全て縮み志向で負のサイクルにはまっているような状況を脱し、明日に向けて正のサイクルを動かす弾みとなるはずだ。
③この意味でも機能強化のために残された時間はさほどない。報告書の射程は「第2期中期目標期間中」即ち2015年度までに、こうした機能強化の大筋を実現する必要がある。
以上長くなりましたが、この報告書で言いたいことは
①国が国立大学にもっと投資すべきである。
②そうすることで国立大学は機能強化(競争力向上)し、国民に責任を持って、国立大学の果たすべき役割を全うすることを約束する。
③そのことが、縮み志向の国や地方を正のサイクルに向けることになる。
と言うことでしょうか。
翻って、静岡県(特に富士市)を見た場合、一年後には大手製紙メーカーが撤退表明しており、県東部(富士市)は産業で取り残される可能性があります。この際、国立大学に限らず、静岡県内の大学の技術、知識を県東部の産業に導入して、産学政協働での振興策が期待されるところです。
①決め手は競争力である。この競争はいろいろなフェーズ、様々な切磋琢磨する対象がある。
②これらの機能強化の実現は、各大学における個性の明確化、ミッションの明示をはじめ、不断の改革の実行や質保証システムの確立、情報開示や、説明責任などを求めている。何よりもまず個々の大学の責任ある努力が重要である。
3)資源を効率的に
①大きな変化の中で、限られた資源の下で、一つの大学で対応するより連携することが、より効率的で生産的な場合もある。実際、地域で、あるいは地域を超えて、教育・研究組織の共同設置や設備等の共同利用、事務処理等の共同化などが着実に進んでいる。
②連携の相手は国立大学に限る必要はない。自らの個性と競争力を確保し、社会に貢献するために、単独で活動するのか、それとも他大学と連携するのか、各大学がしっかり考えるということである。
③国民への約束を果たしてゆく上で、国立大学への運営費交付金の削減や、人件費削減の流れは、まことに不合理なものである。国際的に見て、日本の高等教育に対する公的投資は著しく低い。「ヒト」こそが大学の競争力の源であることを強調したい。
4)2015年度中に実現
①十分な投資で国立大学の機能を強化することが、地域の力を強化し、国の力を強化し、何より大震災からの復興に向けて研究開発と人材育成を強化してゆくことに繋がる。
②このことが、全て縮み志向で負のサイクルにはまっているような状況を脱し、明日に向けて正のサイクルを動かす弾みとなるはずだ。
③この意味でも機能強化のために残された時間はさほどない。報告書の射程は「第2期中期目標期間中」即ち2015年度までに、こうした機能強化の大筋を実現する必要がある。
以上長くなりましたが、この報告書で言いたいことは
①国が国立大学にもっと投資すべきである。
②そうすることで国立大学は機能強化(競争力向上)し、国民に責任を持って、国立大学の果たすべき役割を全うすることを約束する。
③そのことが、縮み志向の国や地方を正のサイクルに向けることになる。
と言うことでしょうか。
翻って、静岡県(特に富士市)を見た場合、一年後には大手製紙メーカーが撤退表明しており、県東部(富士市)は産業で取り残される可能性があります。この際、国立大学に限らず、静岡県内の大学の技術、知識を県東部の産業に導入して、産学政協働での振興策が期待されるところです。
Posted by 富士三合目 at 01:27│Comments(0)
│ビジネス





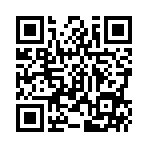



 MKビジネスサポート
MKビジネスサポート





