2011年07月28日
成長か衰退か(日経新聞「経済教室」)
7月28日(木)の日経新聞朝刊に「成長か衰退か」「『危機の経営』で競争力強化」
(伊藤邦雄一橋大学教授)と言う記事が掲載されています。
現在の日本にとって大変示唆に富んだ内容だと思いました。殆ど一紙面全部を使った記事ですので、短いブログでは書ききれないものですが、概要を紹介して見たいと思います。
ポイントは次の3点です。
①金融危機の影響残る日本に震災が追い打ち
②優良企業は察知力、危機意識、スピード強み
③震災で企業が抱える縦割りなどの問題解消
(伊藤邦雄一橋大学教授)と言う記事が掲載されています。
現在の日本にとって大変示唆に富んだ内容だと思いました。殆ど一紙面全部を使った記事ですので、短いブログでは書ききれないものですが、概要を紹介して見たいと思います。
ポイントは次の3点です。
①金融危機の影響残る日本に震災が追い打ち
②優良企業は察知力、危機意識、スピード強み
③震災で企業が抱える縦割りなどの問題解消
先ず①について
・2008年9月に勃発した金融危機リーマン・ショックは日・韓・米の経済動向で比較すると、韓国は既にリーマン危機前の水準は回復し、更に115%位まで伸びており、米国は緩やかながら約95%まで回復している。
・一方日本は、漸くリーマン危機前水準の85%位まで回復していたが、新興国(中国・インドなど)の成長の影響もあり、成長率が伸び悩んでいるところに、震災の追い打ちで再び約80%位まで落ち込んでしまった。
次に②について
・危機は企業の能力を冷酷に試す。危機に耐え得る力を有しない企業は残念ながら断末魔を迎える。
しかし、注目すべきは、日本にもリーマン危機の残酷な試練を超克した企業群が存在する。それらの企業群に共通の行動原理がある。
・PDCA(計画・実行・評価・改善)という企業経営の基礎となる実行力に加えて、「3つのS」を高水準で同時に備えている。
・第一は「察知力(センサー)」で、危機の到来時機や影響の深刻さを事前に感知する能力である。
・第二は「危機意識(センス・オブ・アージェンシー)」で、経営トップが高い危機意識を持つべきなのは当然として、危機意識を社内にいち早く充満させ、危機から脱出する瞬発力と機動力を引き出すことが大切である。
・第三は[高速回転(スピード」である。危機を素早く嗅ぎ取っても、その後のPDCAサイクルが遅ければ時間との勝負である危機には太刀打ち出来ない。「危機の経営」は激烈に変化する環境に合わせ、時機を逸さず的確な戦略を描き、実行するPDCAサイクルを高速化することが肝要である。
最後の③について
・近年日本型経営は「強い現場と弱い本部」、「兵隊一流、将官三流」と揶揄され、又、系列についても「継続性」や「閉鎖性」について問題視されて来た。
・だが、今回の震災では、「現場力と経営力(本部)の同期化」により、日頃から本部として経営システムを磨き上げ、現場が平時のみならず有事にも柔軟に動き易い体制を整えた企業や、協力会社との日頃からの信頼関係を生かし、被災から驚異的に立ち直った会社もある。前者は「セブン&アイ・ホールディングス」であり、後者は「コマツ」等が例示される。「腹の据わった日本国籍のグローバル企業」は危機への「高い耐性力」を示した。
・震災後の各企業の機動力は「日本型経営」に対する批判を跳ね返し、忘れ去られていた日本企業の「新たな競争力」を呼び覚ました。それがまさに「危機の経営」だった。新たな競争力を震災対応時のみで封印してはならない・・。(以下略)
以上今後の日本企業のあり方について示唆に富む内容でした。尚、直接名前の記述はありませんでしたが、「事業継続計画(BCP)」、「事業継続マネジメント(BCM)」もめざすものは同じであり、意を強くしました。
それにつけても、震災後の政府や電力会社の有り様は、「反面教師」として長く日本の歴史に残ることでしょう。
・2008年9月に勃発した金融危機リーマン・ショックは日・韓・米の経済動向で比較すると、韓国は既にリーマン危機前の水準は回復し、更に115%位まで伸びており、米国は緩やかながら約95%まで回復している。
・一方日本は、漸くリーマン危機前水準の85%位まで回復していたが、新興国(中国・インドなど)の成長の影響もあり、成長率が伸び悩んでいるところに、震災の追い打ちで再び約80%位まで落ち込んでしまった。
次に②について
・危機は企業の能力を冷酷に試す。危機に耐え得る力を有しない企業は残念ながら断末魔を迎える。
しかし、注目すべきは、日本にもリーマン危機の残酷な試練を超克した企業群が存在する。それらの企業群に共通の行動原理がある。
・PDCA(計画・実行・評価・改善)という企業経営の基礎となる実行力に加えて、「3つのS」を高水準で同時に備えている。
・第一は「察知力(センサー)」で、危機の到来時機や影響の深刻さを事前に感知する能力である。
・第二は「危機意識(センス・オブ・アージェンシー)」で、経営トップが高い危機意識を持つべきなのは当然として、危機意識を社内にいち早く充満させ、危機から脱出する瞬発力と機動力を引き出すことが大切である。
・第三は[高速回転(スピード」である。危機を素早く嗅ぎ取っても、その後のPDCAサイクルが遅ければ時間との勝負である危機には太刀打ち出来ない。「危機の経営」は激烈に変化する環境に合わせ、時機を逸さず的確な戦略を描き、実行するPDCAサイクルを高速化することが肝要である。
最後の③について
・近年日本型経営は「強い現場と弱い本部」、「兵隊一流、将官三流」と揶揄され、又、系列についても「継続性」や「閉鎖性」について問題視されて来た。
・だが、今回の震災では、「現場力と経営力(本部)の同期化」により、日頃から本部として経営システムを磨き上げ、現場が平時のみならず有事にも柔軟に動き易い体制を整えた企業や、協力会社との日頃からの信頼関係を生かし、被災から驚異的に立ち直った会社もある。前者は「セブン&アイ・ホールディングス」であり、後者は「コマツ」等が例示される。「腹の据わった日本国籍のグローバル企業」は危機への「高い耐性力」を示した。
・震災後の各企業の機動力は「日本型経営」に対する批判を跳ね返し、忘れ去られていた日本企業の「新たな競争力」を呼び覚ました。それがまさに「危機の経営」だった。新たな競争力を震災対応時のみで封印してはならない・・。(以下略)
以上今後の日本企業のあり方について示唆に富む内容でした。尚、直接名前の記述はありませんでしたが、「事業継続計画(BCP)」、「事業継続マネジメント(BCM)」もめざすものは同じであり、意を強くしました。
それにつけても、震災後の政府や電力会社の有り様は、「反面教師」として長く日本の歴史に残ることでしょう。
Posted by 富士三合目 at 22:45│Comments(0)
│ビジネス





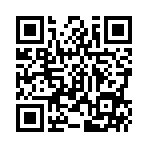



 MKビジネスサポート
MKビジネスサポート





