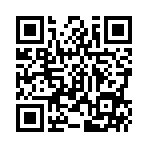2011年05月15日
「家庭で出来る手作りハザードマップ」作って見よう!(事例)
5/12(木)の本ブログで、「家庭で作るハザードマップ」について書いたので、そのやり方を事例で示します。既に、ご存知の方や、もっと上手なやり方もあるかもしれませんが、ご容赦下さい。資料は主として富士市ホームページから頂きました。
1)先ず、パソコンインターネットで「富士市ホームページ(トップページ)」を出します。
2)右側中ほどに「電子サービス」欄があり、その一番上に「ふじタウンマップ」があるのでクリックします。
3)市民向け情報システム「ふじタウンマップ」の利用規定が書いてあり、著作権法上、私用で使用する範囲では無料でよいが、商用目的や営利目的では使用出来ないとあります。
4)そのページの下欄に「関連リンク」「ふじタウンマップ(別ウィンドウ)」があるのでクリックします。
5)「ふじタウンマップ」のページが出るので、自分の住所、又は表示したい施設名を入力し、検索します。
6)アドレスマッチング結果が出て、「マッチングしました」が表示されたら「地図表示」をクリックします・
7)「ふじタウンマップ」のページが表示され、中央に我が家(入力した住所地)があります。(×印)
8)そのページの上欄には「施設情報マップ」「防災マップ」「バリアフリーマップ」等々が並んでおり、お好きな画面を出します。
9)防災マップを表示すると、使用規約文が1ページ分出てきて「同意」をクリックすると自宅周辺の白地図が出てきます。「同意しない」をクリックすると、防災マップは表示されません。この規約の内容は、要約すると、「利用者が自己責任で利用し、利用した結果に対する一切の責任は利用者にあり、市は責任を負わない」と言うものです。これは私の立場からも言えることであり、利用原則ですので、頭に入れて置きましょう。
10)白地図の下の方に「縮尺」が表示されており、1/10,000なら実際の100mが地図上1cm、1/20,000なら0.5cmで表示されます。
11)津波避難対策のためのハザードマップであれば、「5分で500m避難」が一応の目安となりますので、1/10,000(5cm)か、1/20,000(2.5cm)の縮尺が適当でしょう。尚、自宅から海岸や田子の浦港までの直線距離や避難場所までの直線距離も表示出来ます。
12)ここから先は家庭で作る場合を想定すると、「白地図」をコピーして必要な事項は家族で話し合いながら書き込み、完成するのが良いでしょう。
13)ここで、あらかじめ自宅の標高(海抜高さ)を調べておけば、書き込むことが出来ます。→自宅の標高は「標高表示」をキーワードにして、ネット検索すれば、「Google MAP(標高表示)」が出てきて、住所を入力して「移動」をクリックし、次いで「標高取得」をクリックすれば標高が表示されるので便利です。この方法で避難場所等の標高をあらかじめ取得出来ます。
14)パソコン上で標高を書き込む場合は、縮尺欄の下にある、「作図」をクリックすれば、記号、文字、線等を任意の大きさ、色、太さで書き込むことが出来ます。文字を選択して、あらかじめ調べておいた標高数字を入力し、地図上の場所をカーソルで示してクリックすれば書き込まれ、「確定」を押します。(「確定」を押すと表示したものが地図上に固定されます。)
15)前記11)、14)の状態で「印刷」をクリックすると「レイアウト表示」が出ます。A4判でそのままコピーする場合は「A4」でコピーします。貼り合わせてA3判にする場合のレイアウトも選択出来ます。
16)A4判の白地図がコピー出来たらそれに「色鉛筆」、「マジックインキ」等で必要事項を家族で相談しながら書き込みます。書き込む要素は、①自宅の位置及び標高、②学校の位置及び標高、③避難場所及び標高、④避難経路、⑤危険箇所、⑥其々の位置からの直線距離をコンパスで円を描く、⑦その他の必要事項等です。この場合、津波だけでなく、地震による崩壊、落下、がけ崩れ、等の危険要素も書き込んで見て下さい。(特に「高いブロック塀」、「行き止まり」には注意しましょう。)
17)お父さんの勤め先が離れた場所の場合は勤め先を中心に、別のマップを作って見ると、家族で確認が出来ます。又、休日等に家族で散歩しながら家庭で作ったハザードマップを実地検分し、修正すべき点があれば修正しましょう。完成したハザードマップは家族の見える場所に掲示して、時々話題にし、確認し合うと良いでしょう。(手書きしたものを14)のパソコンに戻って仕上げることも出来ます。)
18)津波がどこまで侵入するかは、学術的なことは専門家の想定を待たなくてはなりませんが、おおよそ標高との関係、坂の駆け上がり部分は最大2倍位の高さになった、河川の河口からの逆流が最大40kmになった(河口から5km上流の小学校で被災した)等、東日本大震災で実際に起こったことを参考にして、各自が想定しておくしかないと思います。そのためにも家庭で種々の条件を織り込んでシミュレーションしておくことが大切だと思います。東北地方の教訓からは、「津波てんでんこ(各自がてんでんばらばらに逃げる)」であり、どこへ逃げるか前もって「最悪事態を想定し、訓練しておく」ことでした。
以上長々と書きましたが、参考になれば幸いです。尚、富士市のホームページには、良く見ると大変有用な事項が沢山書かれていることが判りました。有効に活用できればと思いました。
1)先ず、パソコンインターネットで「富士市ホームページ(トップページ)」を出します。
2)右側中ほどに「電子サービス」欄があり、その一番上に「ふじタウンマップ」があるのでクリックします。
3)市民向け情報システム「ふじタウンマップ」の利用規定が書いてあり、著作権法上、私用で使用する範囲では無料でよいが、商用目的や営利目的では使用出来ないとあります。
4)そのページの下欄に「関連リンク」「ふじタウンマップ(別ウィンドウ)」があるのでクリックします。
5)「ふじタウンマップ」のページが出るので、自分の住所、又は表示したい施設名を入力し、検索します。
6)アドレスマッチング結果が出て、「マッチングしました」が表示されたら「地図表示」をクリックします・
7)「ふじタウンマップ」のページが表示され、中央に我が家(入力した住所地)があります。(×印)
8)そのページの上欄には「施設情報マップ」「防災マップ」「バリアフリーマップ」等々が並んでおり、お好きな画面を出します。
9)防災マップを表示すると、使用規約文が1ページ分出てきて「同意」をクリックすると自宅周辺の白地図が出てきます。「同意しない」をクリックすると、防災マップは表示されません。この規約の内容は、要約すると、「利用者が自己責任で利用し、利用した結果に対する一切の責任は利用者にあり、市は責任を負わない」と言うものです。これは私の立場からも言えることであり、利用原則ですので、頭に入れて置きましょう。
10)白地図の下の方に「縮尺」が表示されており、1/10,000なら実際の100mが地図上1cm、1/20,000なら0.5cmで表示されます。
11)津波避難対策のためのハザードマップであれば、「5分で500m避難」が一応の目安となりますので、1/10,000(5cm)か、1/20,000(2.5cm)の縮尺が適当でしょう。尚、自宅から海岸や田子の浦港までの直線距離や避難場所までの直線距離も表示出来ます。
12)ここから先は家庭で作る場合を想定すると、「白地図」をコピーして必要な事項は家族で話し合いながら書き込み、完成するのが良いでしょう。
13)ここで、あらかじめ自宅の標高(海抜高さ)を調べておけば、書き込むことが出来ます。→自宅の標高は「標高表示」をキーワードにして、ネット検索すれば、「Google MAP(標高表示)」が出てきて、住所を入力して「移動」をクリックし、次いで「標高取得」をクリックすれば標高が表示されるので便利です。この方法で避難場所等の標高をあらかじめ取得出来ます。
14)パソコン上で標高を書き込む場合は、縮尺欄の下にある、「作図」をクリックすれば、記号、文字、線等を任意の大きさ、色、太さで書き込むことが出来ます。文字を選択して、あらかじめ調べておいた標高数字を入力し、地図上の場所をカーソルで示してクリックすれば書き込まれ、「確定」を押します。(「確定」を押すと表示したものが地図上に固定されます。)
15)前記11)、14)の状態で「印刷」をクリックすると「レイアウト表示」が出ます。A4判でそのままコピーする場合は「A4」でコピーします。貼り合わせてA3判にする場合のレイアウトも選択出来ます。
16)A4判の白地図がコピー出来たらそれに「色鉛筆」、「マジックインキ」等で必要事項を家族で相談しながら書き込みます。書き込む要素は、①自宅の位置及び標高、②学校の位置及び標高、③避難場所及び標高、④避難経路、⑤危険箇所、⑥其々の位置からの直線距離をコンパスで円を描く、⑦その他の必要事項等です。この場合、津波だけでなく、地震による崩壊、落下、がけ崩れ、等の危険要素も書き込んで見て下さい。(特に「高いブロック塀」、「行き止まり」には注意しましょう。)
17)お父さんの勤め先が離れた場所の場合は勤め先を中心に、別のマップを作って見ると、家族で確認が出来ます。又、休日等に家族で散歩しながら家庭で作ったハザードマップを実地検分し、修正すべき点があれば修正しましょう。完成したハザードマップは家族の見える場所に掲示して、時々話題にし、確認し合うと良いでしょう。(手書きしたものを14)のパソコンに戻って仕上げることも出来ます。)
18)津波がどこまで侵入するかは、学術的なことは専門家の想定を待たなくてはなりませんが、おおよそ標高との関係、坂の駆け上がり部分は最大2倍位の高さになった、河川の河口からの逆流が最大40kmになった(河口から5km上流の小学校で被災した)等、東日本大震災で実際に起こったことを参考にして、各自が想定しておくしかないと思います。そのためにも家庭で種々の条件を織り込んでシミュレーションしておくことが大切だと思います。東北地方の教訓からは、「津波てんでんこ(各自がてんでんばらばらに逃げる)」であり、どこへ逃げるか前もって「最悪事態を想定し、訓練しておく」ことでした。
以上長々と書きましたが、参考になれば幸いです。尚、富士市のホームページには、良く見ると大変有用な事項が沢山書かれていることが判りました。有効に活用できればと思いました。